平日 10:00〜21:00(年末年始除く)
平日 10:00〜21:00(年末年始除く)

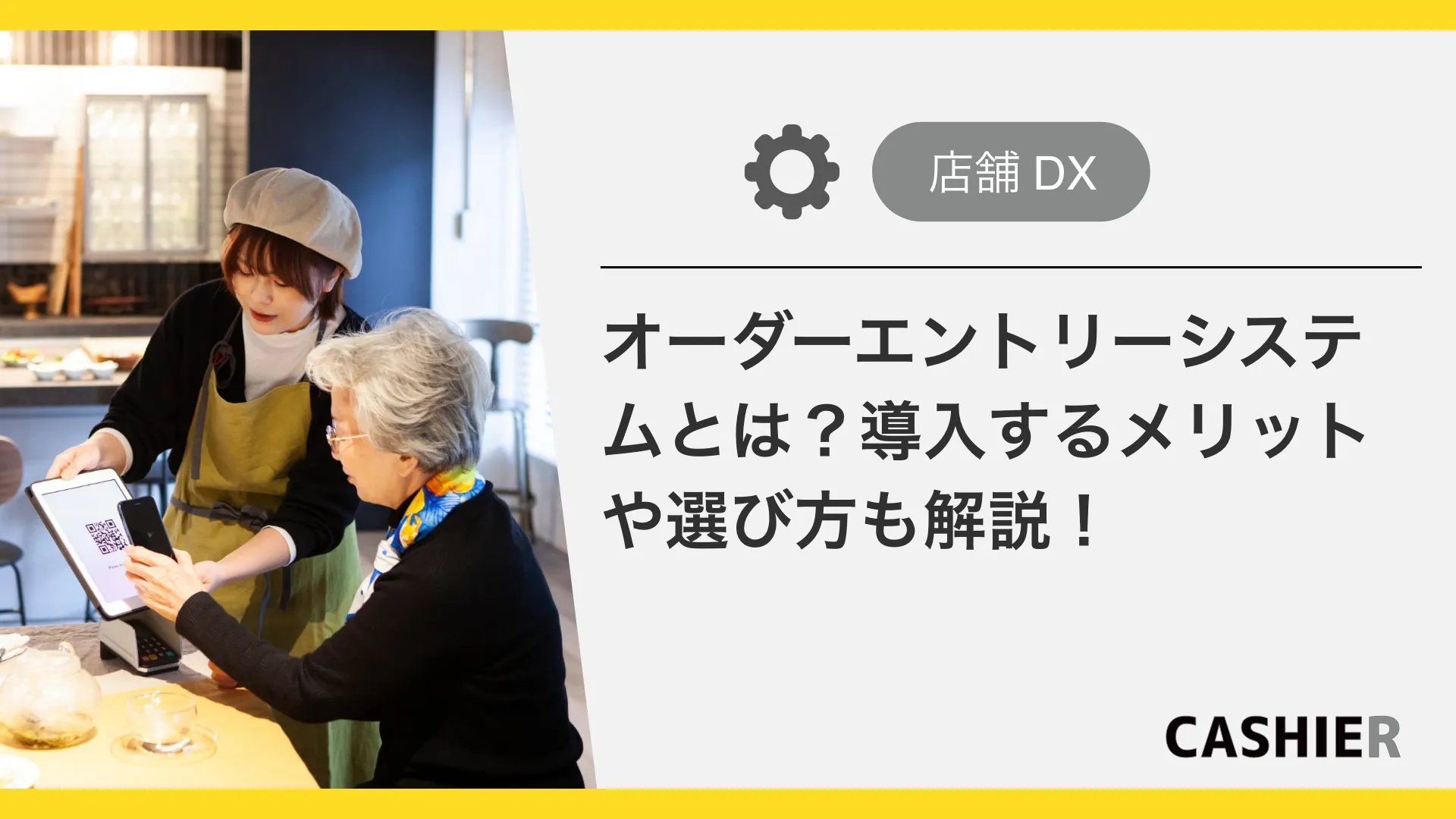 店舗DX
店舗DX 飲食店の注文ミスや人手不足、業務の煩雑化といった課題を解決してくれる「オーダーエントリーシステム」。導入により、注文から調理指示、会計処理までを一気に効率化してくれます。
本記事では、オーダーエントリーシステムの基本的な概要から導入メリット、選び方などを解説します。業務効率化や顧客満足度の向上を目指す店舗経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
この記事では、注文システムの重要性とその機能について解説しています。効率的な注文処理が可能となり、顧客満足度を向上させることができます。また、データ分析による販売管理やメニューの最適化が行え、業務効率が向上します。デジタル化の進展により、リアルタイムでの在庫管理や顧客の嗜好分析が可能となり、競争力のあるビジネス運営が実現します。
オーダーシステムは、飲食店における注文業務をデジタル化し、店舗運営を効率化するための仕組みです。 従来の紙伝票による注文では、スタッフが注文を聞き取り、キッチンに伝達するまでに時間がかかる上、聞き間違いや記入ミスが発生する可能性がありました。 オーダーシステムを導入することで、タブレット端末やハンディ端末を使用し、注文データを即座にキッチンへ送信することが可能です。これにより、注文の正確性が向上し、提供時間の短縮につながります。 このシステムの導入には、業務の効率化や人件費の削減といった多くのメリットも期待できるでしょう。スタッフの業務負担を軽減し、少人数でも円滑に店舗を運営することが可能です。 また、データをもとにオペレーションを最適化することで、サービスの質を向上させることができます。
オーダーエントリーシステムは、注文を受け付けてから調理・料理の提供・会計までの流れを一元管理するシステムです。オーダーエントリーシステムと一口にいっても、以下の3つの方法があります。
オーダーエントリーシステムの方法 | 内容 |
テーブルトップオーダー | 店舗の各テーブルに設置されたタブレット端末を使用し、お客様が注文する方法 |
ハンディオーダー | スタッフがハンディ端末に注文内容を入力する方法 |
モバイルオーダー | お客様がスマホアプリやQRコードを通じて、注文ページから注文を行う方法 |
オーダーエントリーシステムは、注文を受け付けてからすぐにキッチンに情報が共有されるため、迅速かつ正確な料理の提供が可能です。店舗のオーダー業務を大幅に効率化することから、小規模~大規模の飲食店に幅広く導入されています。
オーダーエントリーシステムの主な機能と特徴は以下のとおりです。なお、機種により搭載されている機能は異なります。
機能 | 特徴 |
オーダー入力機能 | スタッフやお客様が端末からメニューを選択して注文を入力できる機能 |
キッチンプリンター連携機能 | 注文内容がリアルタイムでキッチンプリンターに出力され、調理指示がスムーズに伝達される |
テーブル管理機能 | 各テーブルの注文状況や配膳状況を一元管理できる機能 |
POSレジ連携機能 | 注文データをPOSレジと連携させ、会計処理や売上管理がスムーズに行える機能 |
品切れ・残数機能 | 品切れや残り在庫の情報をシステム上で管理し、注文時に表示・制限できる機能 |
ラストオーダー管理機能 | ラストオーダーの時間になると自動で注文を制限するなどの管理ができる機能 |
オーダーエントリーシステムには、上記以外にもさまざまな機能があります。導入を検討する際は、自店舗の課題を洗い出し、どの機能が必要かを明確にしたうえで最適なシステムを選ぶことが重要です。
オーダーエントリーシステムを導入するメリットは以下の4つ挙げられます。
オーダーエントリーシステムを導入することで、店舗の業務効率化に大きく貢献します。紙の伝票で注文を取る方法では、注文の聞き間違いや記入ミスが起きやすく、キッチンまで伝票を運ぶ手間もかかっていました。
しかし、オーダーエントリーシステムなら、注文処理が自動化され、ホールスタッフがキッチンまで伝える必要がありません。注文内容はリアルタイムでキッチンに共有されるため、配膳ミスやオーダー漏れの防止にもつながります。
注文業務が効率化されれば、スタッフの負担軽減や人員を削減することも可能です。結果として、限られた人員でも効率よく店舗運営を行うことが可能になるでしょう。
オーダーエントリーシステムを導入すれば、注文から提供までの時間を短縮できるため、顧客満足度の向上が期待できます。スタッフが都度オーダーを確認しなくても、正確な情報がキッチンへ自動で送信されるため、提供ミスのリスクも減少します。
また、注文業務がなくなるため、その浮いた時間分を接客やフォローなど、サービスの質を高めることに注力できる点もメリットです。お客様の来店履歴や注文傾向をシステム上で把握できれば、リピーターへ最適な提案も可能となります。
オーダーエントリーシステムをPOSレジと連携させることで、注文情報・売上データ・在庫情報などを一元管理できます。売上データや在庫状況をリアルタイムで把握できるため、店舗の運営状況を数値で把握でき、ムダや機会損失を防ぐことが可能です。
また、POSレジにはデータ分析機能が備わっており、売上推移や時間帯別の注文傾向、人気メニューなどを可視化できます。売れ筋を踏まえたメニュー改善や、無駄のない仕入れがしやすくなり、店舗運営の意思決定を適切に行えるようになります。
データをうまく活用して効果的なマーケティング戦略を構築できれば、売上アップにも貢献するでしょう。
オーダーエントリーシステムの導入は初期費用こそかかるものの、長期的に見ると、コスト削減に貢献する点がメリットです。注文処理の自動化によりホールスタッフの業務負担が軽減され、人件費の削減につながります。
また、入力ミスや聞き間違いによる再調理が減ることで、食材のロスも最小限に抑えられます。さらに、POSレジの在庫管理機能と連携すれば、在庫の最適化が可能になり、過剰在庫のリスクも軽減することが可能です。
手作業で行っていた業務の多くをシステムで効率化できるため、運営コストの見直しと収益の向上に大きく貢献するでしょう。
ホワイトペーパー設置:オーダーシステムを活用した飲食店のDX推進ガイド
 ここでは、店舗端末を利用したオーダーシステムの種類をご紹介します。
ここでは、店舗端末を利用したオーダーシステムの種類をご紹介します。
ハンディオーダーとは?種類やメリットを徹底解説 ハンディオーダーシステムとは、スタッフが専用のハンディ端末を利用し、お客様からのオーダーを取るシステムです。最近ではスマホ型の端末を利用する企業が増えており、直感的な操作が可能になっています。 受けたオーダーを端末からすぐに厨房に送信できるため、時間短縮につながりますが、導入には端末を用意することが必要です。 ハンディオーダーシステムの詳細は、以下の記事をご覧ください。 関連記事:CASHIER「ハンディオーダーシステム」
テーブルオーダーシステムは、各テーブルに専用のタブレットを用意し、お客様が自分で商品を選んで厨房に直接オーダーを送信するシステムです。注文を受けるスタッフがいらなくなるため、その他の業務に専念できるようになります。 また、セルフレジと連携して利用すると、注文から会計までの業務のすべてをお客様自身に行っていただくシステムを構築できます。一方で、導入するにはタブレット端末が欠かせません。 テーブルオーダーシステムの詳細は、以下の記事をご覧ください。 関連記事:CASHIER「テーブルオーダーシステム」
つづいて、お客様のスマホを利用したオーダーシステムの種類をご紹介します。 これらの特徴として、導入により特別な機器を購入する必要はなく、初期費用を抑えられます。お客様自身のスマホから注文するため、衛生的なオーダーや会計が可能です。
スマホオーダーシステムとは、お客様のスマホから注文するシステムです。店舗側が用意したQRコードを読み取ってもらうことでメニューが表示され、注文を厨房に送信できます。 お客様自身で注文履歴や配膳状況の確認が可能なため、スタッフの負担をより軽減できるでしょう。 スマホオーダーシステムでは、退店時にまとめて会計する事後決済が採用されています。 スマホオーダーの詳細は、以下の記事をご覧ください。 関連記事:CASHIER「スマホオーダー」
モバイルオーダーシステムとは、お客様のスマホを通じて、店外・店内のどちらからでもオーダーと決済が可能なシステムです。テイクアウトの場合には、事前に店舗のWebページやアプリなどから商品を購入。その後、指定時間に合わせて来店し商品を受け取るというものです。 お客様の商品提供までの待ち時間を短縮できるとともに、思い立ったらその場で購入できるため、お客様の購買機会を逃がしません。そのため、売上の向上も期待できます。 モバイルオーダーシステムでは、事前決済形式のみに対応しています。 スマホオーダーの詳細は、以下の記事をご覧ください。 関連記事:CASHIER「モバイルオーダー」
ここでは、オーダーエントリーシステムを導入した店舗の成功事例をご紹介します。
和牛焼肉専門店「うし牛」では、新規開業時にスタッフ不足を見越してCASHIERのテーブルオーダーを導入しました。来店客自身が注文できる仕組みにより、ホール業務の負担が大幅に軽減され、スタッフの人数を最小限に抑えた効率的な営業体制を実現しています。
オーダーは自動でキッチンに送信されるため、提供スピードも向上し、顧客満足度アップにもつながっています。また、飲み放題利用時の追加注文も増え、売上にも好影響が出ているとのことです。
導入費用は補助金を使わずとも低コストで抑えられ、特に初期費用と月額費用の安さが決め手になっています。実際に導入後半年で多くの課題が解消され、投資回収までのスピードも早く、焼肉店のような中規模〜繁忙業態にも相性が良いシステムです。
>>導入事例はこちら
鉄板焼き店「Tetsu坊」では、手書き伝票による注文ミスや会計漏れが課題でしたが、CASHIERのハンディ導入により大きく改善しています。オーダーが即時に記録・反映されることで、ミスが激減し、会計もスムーズになっています。
操作も直感的で使いやすく、忙しい時間帯でもお客様を待たせず対応可能になりました。ハンディ導入が現場の負担を軽減し、お客様の満足度向上にも直結した好事例といえるでしょう。
>>導入事例はこちら
東京都で営業する「海鮮とと金」では、店主が一人で切り盛りするスタイルに合わせ、CASHIERのテーブルオーダーを導入しました。仕入れ状況に応じて毎日変わる刺身メニューも、自身で簡単に更新できる点が決め手でした。
通信の安定性や注文ミスの軽減にもつながり、1人営業でも無理のない店舗運営を実現しています。5年間のコスト試算や飲み放題機能の充実も、導入を後押しするポイントとなりました。
>>導入事例はこちら
香川発祥のうどん店「おにやんま」では、店舗運営の効率化を目的にCASHIERのキャッシュレス専用券売機を導入しました。現金対応では小銭の補充やエラー処理に手間がかかり、人手不足の中で1人がそれに割かれる状況もありました。
特に札詰まり・小銭詰まりのトラブルが頻発していたことから、これらの課題を根本から解消するために現金を廃止。導入直後は現金不可への対応に苦労もあったものの、現在では来店者にもキャッシュレス決済が定着し、業務効率が大きく向上しています。
 近年、オーダーシステムはAI技術やキャッシュレス決済との連携、データ分析機能の強化により進化を続けています。 AIを活用したオーダーシステムでは、顧客の過去の注文履歴をもとにパーソナライズされたメニューを提示し、リピート率の向上を狙うケースが増えています。また、キャッシュレス決済と統合することで、スムーズな会計処理が可能となり、回転率の向上が進んできました。 さらに、注文データを分析することで、売れ筋商品の把握や需要予測が可能となり、より効率的な店舗運営が実現するでしょう。
近年、オーダーシステムはAI技術やキャッシュレス決済との連携、データ分析機能の強化により進化を続けています。 AIを活用したオーダーシステムでは、顧客の過去の注文履歴をもとにパーソナライズされたメニューを提示し、リピート率の向上を狙うケースが増えています。また、キャッシュレス決済と統合することで、スムーズな会計処理が可能となり、回転率の向上が進んできました。 さらに、注文データを分析することで、売れ筋商品の把握や需要予測が可能となり、より効率的な店舗運営が実現するでしょう。
スマホオーダーシステムは、顧客が自身のスマートフォンを利用して注文を行う仕組みです。正確性の向上や待ち時間の短縮、多言語対応といったメリットがあります。 外国人観光客が多いエリアでは、多言語対応のオーダー画面を提供することで、円滑な注文を実現できます。また、スタッフを介さずに注文できるため、オーダーミスの削減や業務負担の軽減も可能です。 福岡県のラーメンチェーン「九州筑豊ラーメン山小屋」では、LINEミニアプリを活用したセルフオーダーシステムを導入しました。これにより、スタッフが注文を取りに行く必要がなくなり、業務効率の向上が図られています。 さらに、利用者の約8割がLINE経由で注文を行い、オーダーミスや会計ミスが減少したことで、スタッフの教育時間も短縮されたということです。
モバイルオーダーシステムは、顧客がスマホやタブレットを使って事前に注文し、店舗での受け取りをスムーズにする仕組みです。 主にテイクアウトやデリバリーに適用されることが多く、店舗の待ち時間を大幅に削減できます。カフェやファストフード店では、事前注文を活用することでピークタイムの混雑を緩和し、オペレーションの効率化が図られます。 2024年4月に開業した東急プラザ原宿「ハラカド」では、クラウドPOSシステムとモバイルオーダーシステムを連携導入しました。これにより、複数の飲食店舗のメニューを一括で注文・決済できる環境を整え、顧客の利便性向上と業務の効率化を実現しています。 
オーダーシステムを導入する際には、いくつかの課題に留意する必要があります。まず、スタッフの習熟度の差です。特に、デジタル機器の操作に慣れていないスタッフにとっては、オーダーシステムの使いこなしが難しく、スムーズな運用が妨げられる可能性があります。 導入前に十分な研修を行い、システムの操作方法を統一することが重要です。 システム障害時の対応も考慮する必要があります。オーダーシステムが正常に動作しなくなった場合、店舗運営に大きな支障をきたすため、通信環境のバックアップや手動対応の手順を整えておくことが不可欠です。 たとえば、Wi-Fiが不安定な店舗では、有線接続やモバイル回線を活用できる環境を整えるとよいでしょう。 また、顧客の使用感も無視できません。タブレットやスマホを利用したセルフオーダー方式では、システムの操作が直感的でないと、注文に手間がかかり、かえって顧客のストレスにつながります。 画面のデザインや操作性をシンプルにし、誰でも簡単に注文できる設計を採用することが、満足度向上につながります。 導入時には試験運用を行い、実際の顧客の反応を見ながら改善していくことが求められます。
オーダーシステムを安定的に運用するためには、トラブル発生時の対応策を事前に準備しておくことが重要です。例えば通信障害が起きた場合、店舗のネットワーク環境を確認し、必要に応じてモバイル回線や別のWi-Fiネットワークに切り替えることができます。また、LANケーブルを使用して有線接続のオプションを用意しておくことも有効です。 機器の故障に対しては、予備の端末を準備しておくことが推奨されます。特に、タブレットやハンディ端末を使用する場合は、1〜2台の予備機を確保し、トラブル発生時に即座に交換できる体制を整えることが必要です。 また、操作ミスへの対応策として、スタッフ向けのトレーニングやマニュアルを整備し、基本的な操作手順を周知しておきましょう。 システムが利用できない場合に備え、手書き伝票を用意し、アナログな方法でも注文が受けられる体制を構築しておくことで、万が一の事態にもスムーズに対応できます。
オーダーシステムを導入する際は、店舗運営に適したシステム選定が重要です。ポイントは以下の3つです。
オーダーシステムの選定では、店舗の規模や業態に適した機能を見極めることが重要です。例えば、回転率の高いファストフード店では、モバイルオーダーやセルフレジ機能が有効です。一方、フルサービスのレストランでは、ハンディ端末によるテーブルオーダーが適しています。 また居酒屋やカフェでは、タブレット型セルフオーダーシステムを導入することで、スタッフの業務負担を軽減しながら効率的なオペレーションを実現できます。 選定の際にはチェックリストを活用し、条件を満たしているかを確認しつつ、導入後の運用イメージを具体化することで、より適切なシステム選びが可能になります。
オーダーシステムを導入する際は、初期費用とランニングコストを考慮し、費用対効果を試算することが不可欠です。 システムの種類によって価格帯は異なり、ハンディオーダー端末は比較的低コストで導入できる一方、タブレット型セルフオーダーは初期投資が大きくなる傾向にあります。 ただ、後者は長期的に見ると、人件費の削減や業務効率化による売上向上が期待できるのが強みです。導入前にコストとメリットを比較し、自店舗の経営に適したシステムを選びましょう。
システムの導入後、スムーズな運用を実現するためには、操作性と使いやすさが重要なポイントです。デジタル機器の使用に慣れていないスタッフでも直感的に操作できるシステムを選び、スムーズな導入を進めましょう。 タッチ操作の反応速度、画面デザインの分かりやすさ、サポート体制の充実度などを事前に確認し、実際のデモ画面を試すことが有効です。導入前にトライアル期間を設け、スタッフが問題なく扱えるかを評価することも、失敗を防ぐ重要なステップとなります。 
オーダーエントリーシステムは、飲食店の注文業務を効率化し、人手不足やミスを解消するツールです。業態や課題に応じて導入することで、顧客満足度や売上向上も期待できます。
導入を検討する際は、機能・費用・使いやすさを見極め、自店舗に最適なシステムを選びましょう。 CASHIERのオーダーエントリーシステムなら業界最安水準で導入できる上、飲食店の業務負担を大幅に軽減することができます。
オーダーエントリーシステムを検討されている方は、ぜひ一度お問合せください。
