
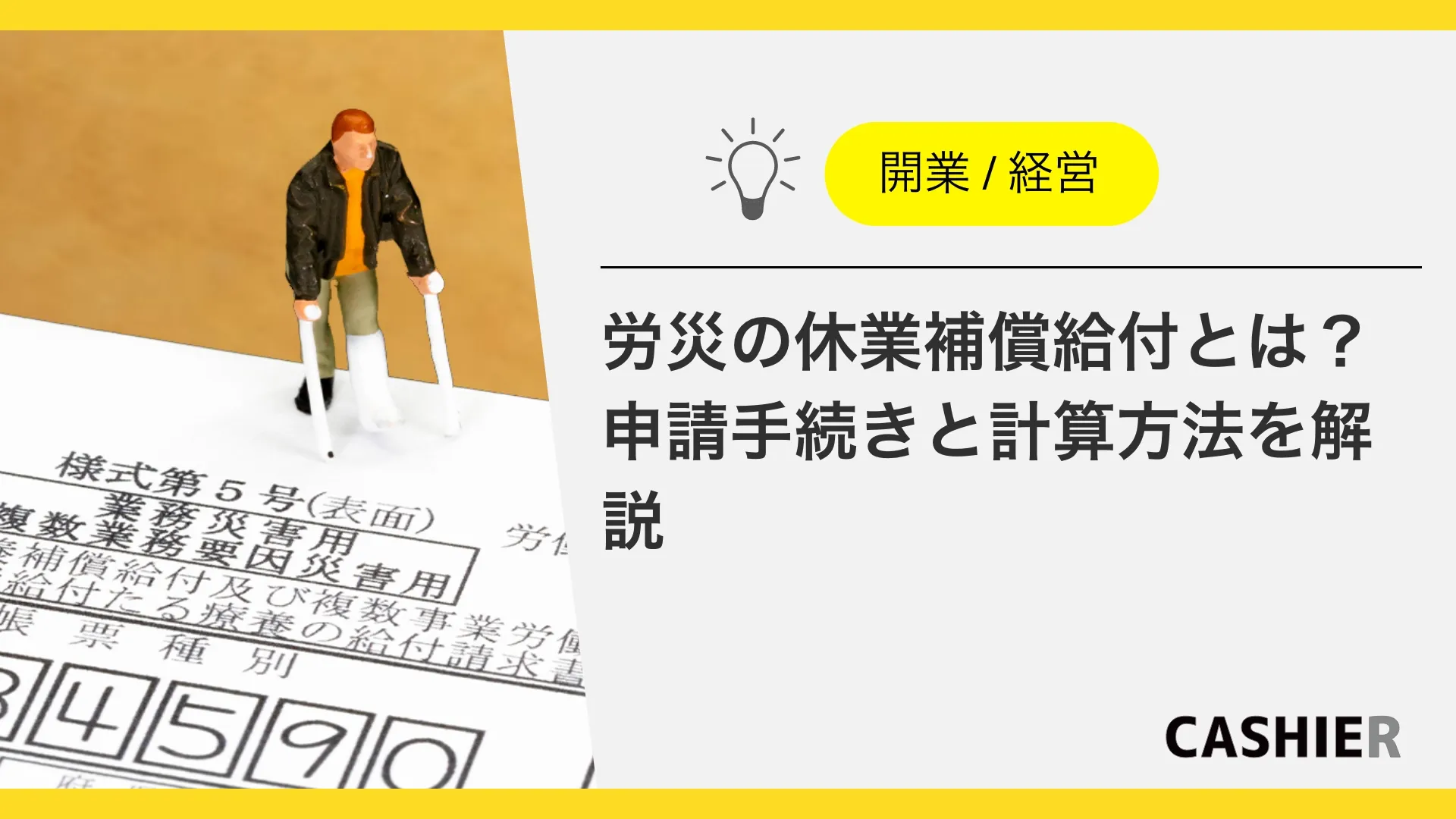 開業/店舗経営
開業/店舗経営 飲食店や小売店を開業するにあたって、「もしスタッフや自分がケガをしたらどうすれば?」という不安を感じたことはありませんか。
労働中や通勤中のケガ・病気に備える制度が労災保険です。なかでも「休業補償給付」は、ケガで働けなくなった際に支払われる給付金で、生活や経営を支える大切な仕組みです。
従業員を守りながら、自分の経営も守るための備えを、開業前に理解しておいてください。
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
本記事では、労災の休業補償給付の基本から、支給額の計算方法、そして申請手続きの流れまでをわかりやすく解説します。 また、混同されやすい「休業手当」との違いにも触れ、開業前に押さえておくべきポイントを整理しました。
飲食店や小売店の現場では、火傷や切り傷、転倒、交通事故など、日常的にリスクが潜んでいます。「うちは大丈夫」と思っていても、事故は思いがけない瞬間に起こるもの。
万が一の備えとして、労災保険の仕組みを理解しておくことは開業準備の重要なステップです。
従業員がケガをすれば治療費や休業補償が発生し、オーナー自身がケガをすれば営業そのものが止まることもあります。
そんなときに頼れるのが、労働中や通勤中の事故を国が補償する「労災保険制度」です。
特に「休業補償給付」は、働けない期間の生活を支える重要な仕組みです。労災の理解は“もしもの保険”にとどまらず、安心して働ける店舗づくりの基盤でもあります。
制度を整えておくことで、スタッフの信頼を得やすくなり、採用や定着にもプラスに働きます。
飲食業では、火傷・切り傷・転倒が最も多く報告されています。たとえば、油のはねによる火傷、包丁やスライサーでの負傷、床の清掃中に滑って転ぶ事故などです。
小売業では、商品搬入時の腰痛や筋肉損傷、脚立からの転落といったケースも少なくありません。
また、配達や仕入れの途中に発生する交通事故も「通勤災害」として労災の対象になります。
どんなに安全管理を徹底していてもゼロリスクにはできません。
だからこそ、制度としてのセーフティネットをあらかじめ用意しておくことが、店舗経営の安定につながります。
労災保険の目的は、従業員の生活を守ることだけではありません。
現場で働くオーナーや家族従業員も、「中小事業主特別加入制度」に加入すれば、同じように補償を受けられます。
たとえば、仕込み作業中に手を切って営業できなくなった場合や、出張・仕入れ中に交通事故にあった場合でも給付を受けることが可能です。
開業前にこの制度を知っているかどうかで、リスク対応のスピードが大きく変わります。
「スタッフも自分も守る」という意識を持つことが、安定した店舗運営の第一歩です。
事故は予防できても、ゼロにはできません。だからこそ、「制度で守る」という選択が重要になります。
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中や通勤中のケガ・病気・死亡に対して、国が補償を行う制度です。
一般的な健康保険とは異なり、業務に起因するケガであれば、医療費や休業中の所得補償がすべてカバーされます。
補償内容には「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」などがありますが、店舗経営者が特に知っておくべきなのは、従業員や自分がケガで働けなくなった期間の収入を支える『休業補償給付』です。
「休業補償給付」は、労災により4日以上仕事を休む場合に支給されます。
休業1〜3日目は“待期期間”とされ、この間は会社が労働基準法上の休業補償(平均賃金の60%以上)を支払う義務があります。
4日目以降は国から休業補償給付が支給されます。
つまり、会社と国が連携して補償を分担する仕組みです。
💡補足
「経営上の都合」「天候や設備トラブル」など、業務災害に該当しない休業は、労災ではなく休業手当(会社負担)の対象です。
休業補償給付の支給額は以下の式で計算されます。
給付基礎日額 × 60%(休業補償給付)+ 20%(休業特別支給金)= 実質80%の補償
「給付基礎日額」とは、ケガをする直前3か月間の賃金を基に算定される“日額ベースの基準金額”です。
たとえば、1日あたりの給付基礎日額が10,000円なら、
支給期間に上限はなく、療養が続く限り受け取ることが可能です。
ただし、長期にわたる場合は医師の再診断書など追加書類が必要です。
✅ 経営者メモ
「中小事業主特別加入制度」に加入しているオーナーも、同様に休業補償給付を受け取ることができます。開業時に労働保険事務組合を通じて手続きを済ませておくと安心です。
休業補償給付を受け取るには、次の3条件を満たす必要があります。
支給期間は療養が終わるまで無期限です。
症状固定後に障害が残れば「障害補償給付」に、死亡事故の場合は「遺族補償給付」に切り替わります。
労災保険は、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わずすべての労働者が対象です。
スタッフを1人でも雇用した時点で、事業主には加入義務が生じます。
「家族経営だから」「短時間バイトだから」という理由で対象外にはなりません。
経営者自身は原則対象外ですが、特別加入制度を利用すれば補償を受けられます。
労災保険は「労働者」であるかどうかで判断され、雇用形態ではなく使用従属性が基準です。
勤務時間や雇用期間に関わらず、指揮命令下で働く人は全員加入対象です。
💡ワンポイント
労災保険料は全額事業主負担であり、従業員の給与から天引きするものではありません。
現場に立つ経営者や家族従業員は「中小事業主特別加入制度」によって補償対象となります。
申請は地域の労働保険事務組合を通じて行い、書類提出先は所轄の労働基準監督署です。
この制度を利用することで、仕込み中のケガや配達中の事故など、実務上のリスクにも対応できます。
審査を経て支給決定後、1〜2か月を目安に振込。
特別加入者は「様式第8号の2」を使用します。
労災保険は、従業員だけでなく店舗を守る制度でもあります。
未加入のまま事故が起きると、治療費・給与補償・代替人員費をすべて自己負担することになります。
また、労基署の指導や罰則対象となるケースもあります。
経営者自身のケガも、特別加入で補償対象にできます。
労災保険料は業種ごとに料率が決められており、飲食・小売業は賃金総額の約0.3〜0.5%が目安です。
たとえば、年間賃金300万円なら保険料は9,000〜15,000円程度(※実際の料率は業種区分で異なります)。
このわずかな負担で、万が一の際に数十万〜数百万円の損害を防げます。
チェック項目 | 内容 |
□ 労災保険への加入手続き | 労働保険関係成立届・概算保険料申告書を提出 |
□ 中小事業主特別加入制度の確認 | オーナー自身が現場に立つ場合は必須 |
□ 安全衛生マニュアルの整備 | 火傷・転倒など具体的な事故防止策を明文化 |
□ 労災申請書類のテンプレート準備 | 様式第8号・第23号などを事前に確認 |
□ 従業員への安全教育 | 初出勤時に労災対応・応急処置のルールを共有 |
□ 保険料・申請窓口の確認 | 所轄労基署・労働保険事務組合の連絡先をメモ |
