
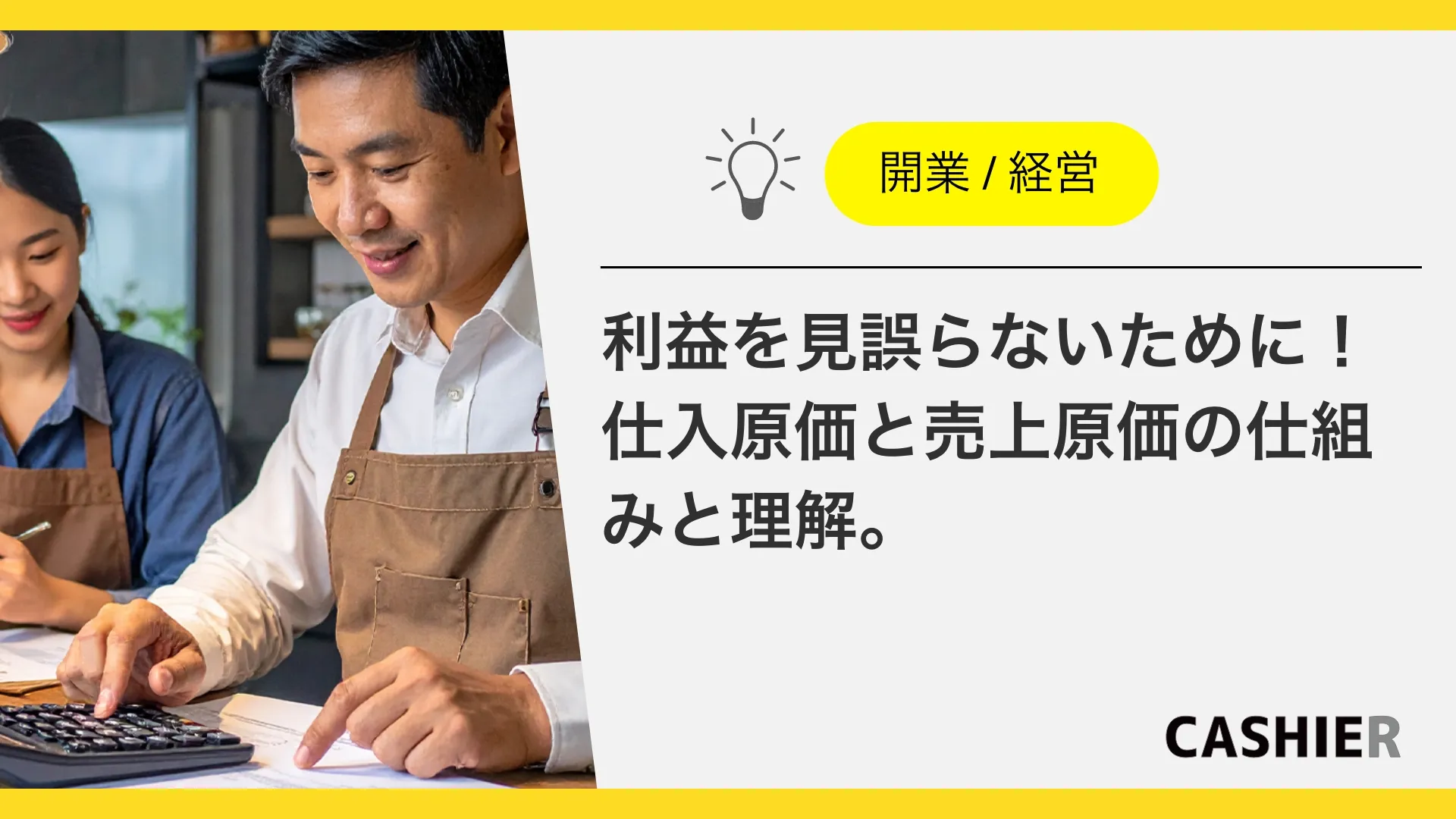 開業/店舗経営
開業/店舗経営 お店を始める準備をしていると、「仕入れた分はそのまま経費になる」と思ってしまいがちです。
しかし、実際には仕入れた時点ではすべてが“原価”になるわけではありません。
仕入れ原価と売上原価は、費用として計上されるタイミングが異なるため、
この仕組みを理解していないと、実際の利益を見誤ってしまうことがあります。
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
この記事では、開業前に知っておきたい「仕入れ原価と売上原価の関係」をわかりやすく整理しながら、 正確な利益率の算出や在庫管理、ムダな仕入れの防止につなげる考え方を解説します。 数字に強くなることで、感覚ではなく“データで経営判断できる店づくり”が可能になります。
仕入れ原価と売上原価は、どちらも“原価”という言葉を使いますが、
指している中身と費用化されるタイミングが異なります。
仕入れ原価は、その名の通り「商品・材料を調達するためにかかったコストの総額」で、
仕入価格に加えて送料・関税・仕入手数料・検品費用などの付随費用を含めます。
一方で売上原価は、ある会計期間の売上に対応するコストだけを取り出したもの。
式で表すと、
売上原価 = 期首在庫 + 当期仕入 - 期末在庫
となります。
ポイントは、お金を払った瞬間=費用ではないということ。
買ったけれどまだ使っていない・売れていない分は在庫(資産)に残し、
売上に対応した分だけを費用化します(対応原則)。
この考え方を押さえると、利益の“見え方のズレ”がなくなり、
価格設定や仕入れ量の判断がブレにくくなります。
飲食店の材料費は、その期間に実際に使用した分だけが売上原価になります。
月初に冷凍庫にあった肉(期首在庫)と、今月買い足した食材(当期仕入)を合計し、
月末時点で残っている材料(期末在庫)を差し引くと、その月に提供した料理に対応する材料費が出ます。
例)期首在庫2万円 + 当期仕入10万円 - 期末在庫3万円 = 売上原価9万円
「まとめ買いしたから今月の原価が高い」という感覚は誤りになりがちです。
在庫に残っている分は今月の費用ではないため、使用量ベースで考えることが重要です。
この仕組みを理解しておくと、翌月の仕入れ計画や発注量の調整にも活かせます。
その結果、原価率やメニュー設計の精度が上がります。
小売の仕入は、販売して初めて費用化されます。
期首在庫と当期仕入の合計から、期末時点で店頭や倉庫に残っている商品を引くことで、
その期間に実際に売れた商品の仕入コストだけを売上原価として計上します。
例)期首在庫30万円 + 当期仕入120万円 - 期末在庫50万円 = 売上原価100万円
ここで大切なのは、仕入の支出(キャッシュの減少)と費用化のタイミングを分けて考えること。
仕入れが先行すると現金は減りますが、売れていない限り費用化されません。
だからこそ、在庫回転とキャッシュフローの管理が業績に直結します。
共通の落とし穴は、「支出=その期の費用」と短絡してしまうことです。
会計では、売上と費用を同じ期間で対応させる(対応原則)ため、
買っただけ・仕込んだだけの分は在庫(資産)として繰り越します。
この仕組みを運用するうえで要になるのが棚卸です。
月末に在庫数量と単価を確認し、金額に換算して評価し、
式(期首+仕入-期末)に反映させて初めて、その月の実態に即した売上原価が確定します。
結果、原価率・粗利・損益の数字がぶれにくくなり、
価格改定や発注量の意思決定が理論立てて行えるようになります。
仕入れ原価と売上原価の違いは、「会計のルール」と「棚卸」の考え方から生まれます。
多くの人が「買った=費用」と思いがちですが、会計上は“売上に対応する分だけ”を費用として計上するという原則(対応原則)があります。
つまり、仕入れたものがまだ使われていなければ、それは“費用”ではなく“資産”として残す必要があるのです。
その区別を正確につけるために欠かせないのが、棚卸(在庫の確認)です。
棚卸とは、期末(決算や月末など)に在庫を数えて、その価値を金額に換算する作業のことです。
飲食店なら冷蔵庫や倉庫の中にある食材を、小売店なら店頭やバックヤードの商品の数を数えて、1つずつ金額を算出します。
この作業によって、どれだけの在庫が「使われなかった=次期に持ち越す資産」なのかが明確になり、
それを式(期首在庫+当期仕入-期末在庫)に反映させることで売上原価(使われた分)が確定します。
仕入れ原価の段階では、まだ費用化できるかどうかが不明確です。
そこで在庫の残りを「引く」ことで、当期の売上に対応した分だけを取り出します。
この調整を行わないと、「仕入が多い月は赤字、少ない月は黒字」といったブレが発生し、
経営判断を誤る原因になります。
棚卸をきちんと行うことは、損益を正しく反映させるための前提条件なのです。
棚卸は「やればいい」というものではなく、精度と継続性が大切です。
具体的には、
・棚卸の基準日を毎月固定する
・単価を最新の仕入価格に合わせて更新する
・廃棄やロス分も記録し、棚卸差異を減らす
といった工夫が欠かせません。
これらをPOSシステムや在庫管理アプリと連携させると、棚卸作業を効率化しながらデータ精度を維持できます。
正確な在庫データがあれば、売上原価の算出も自動化でき、経営数字がブレにくくなるという大きなメリットがあります。
月次で小さく始め、棚卸差異を毎回振り返る習慣づけが精度向上の近道です。
仕入れ原価と売上原価の仕組みを理解し、正確に原価を計算できるようになると、
経営の見え方が一気に変わります。
感覚的に「なんとなく儲かっている」「仕入れが多い月は厳しい」と捉えていた数字が、
根拠をもって判断できる指標になります。
ここでは、正しい原価計算によって得られる3つの主な効果を紹介します。
まず1つ目は、利益率を正確に把握できるようになることです。
原価を誤って計上すると、実際よりも利益が小さく(あるいは大きく)見えてしまうことがあります。
仕入れと売上のタイミングを揃えて原価を算出すれば、各商品の原価率・粗利率・利益率が正確に算出でき、
「どの商品が稼ぎ頭なのか」「どこを見直すべきか」が明確になります。
数字を根拠にメニュー価格を調整したり、仕入先との交渉を行うことができるようになり、
感覚ではなくデータに基づいた価格戦略が取れるようになります。
結果として、粗利の安定と改善余地の特定が容易になります。
原価計算の仕組みを理解すると、「どれだけ仕入れて、どれだけ使っているか」が明確に見えるようになります。
これにより、過剰な仕入れや余剰在庫を防げます。
必要な分だけを効率的に仕入れることが可能になり、スペースやコストを無駄にしません。
在庫を減らすことは単にスペースを節約するだけではなく、現金を守ることにも直結します。
在庫は“眠っているお金”とも言えるため、適正在庫を保つことでキャッシュフローが改善し、
資金繰りにも余裕が生まれます。
「原価管理=在庫管理」と考えると、その重要性がより実感できると思います。
まずは“適正在庫の目安(在庫日数・回転率)”を決めて運用してみましょう。
3つ目は、仕入れの判断が的確になることです。
仕入れ原価と売上原価のデータを定期的に比較すると、季節・天候・イベントなどによる需要の変化が見えてきます。
この傾向を掴むことで、必要なタイミング・必要な量を把握でき、
ムダな仕入れや欠品を防ぐ精度の高い発注判断が可能になります。
特にPOSレジや在庫管理システムを活用すれば、
「売上データ × 仕入データ」をもとに自動で在庫推移を分析できます。
こうしたデータの蓄積が、経験や勘に依存しない発注判断を支えます。
結果として、誰が担当してもブレない“再現性のある経営スタイル”へ移行できます。
仕入れ原価と売上原価の違いは、会計上の知識にとどまらず、
お店の経営を安定させるための“数字の土台”です。
仕入れた時点ではまだ「費用」ではなく、売れた・使った時に初めて「原価」として計上される。
このタイミングの違いを理解しておくことで、実際の利益が正確に見え、
価格設定や仕入れ、在庫管理の判断を迷いなく行えるようになります。
また、こうした数字の管理は、手作業ではどうしても手間がかかり、誤差も生じやすい部分です。
CASHIERなら、POSレジと在庫データを自動で連携し、
仕入・販売・在庫を一元管理できます。
仕入れや販売のデータから原価率や在庫推移をリアルタイムに把握できるため、
経営判断のスピードと精度が格段に向上します。
原価を“数字”で捉えることは、感覚に頼らない経営への第一歩です。
今日から、売上と費用のタイミングを意識して、数字に強い店づくりを進めていきましょう。
