
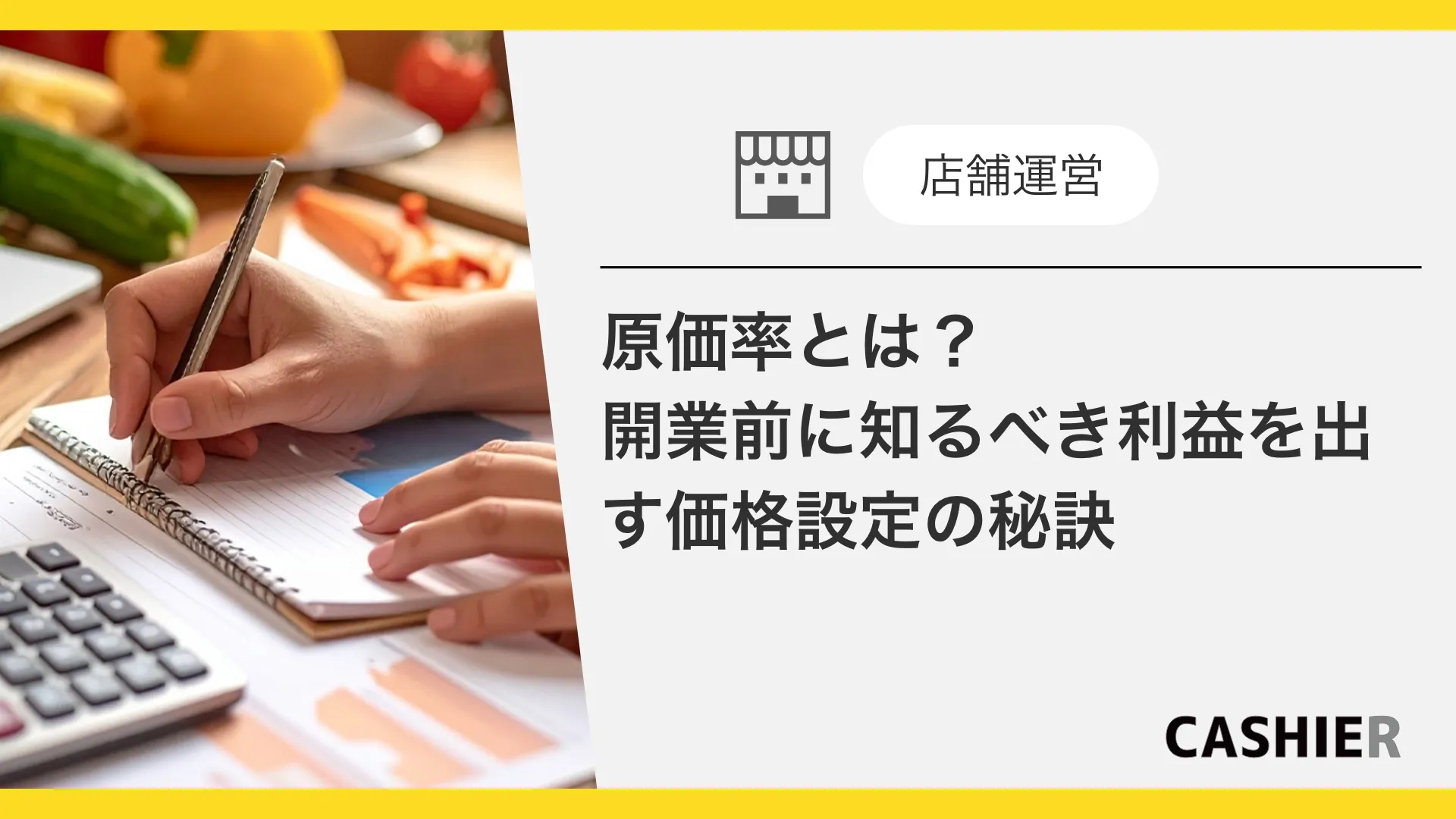 店舗運営
店舗運営 「仕入れ原価にいくら上乗せすれば、ちゃんと利益が出るの?」
最近は原材料や人件費が高騰しており、価格設定の見直しがますます重要に。飲食店や小売店の開業を考える方にとって、価格設定の悩みは避けて通れないテーマです。そんなときにぜひ知っておきたいのが、「原価率」という考え方。
原価率を理解すれば、適正な価格を“逆算”して決められるようになり、「売れているのに利益が出ない」といった事態を防ぐことができます。
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
この記事では、原価率の意味・計算方法・業種別の目安について、開業準備中の方にもわかりやすく解説。さらに、価格設定で損をしないためのコツや、イートインとテイクアウトの違いなど、具体的な事例も交えてお伝えします。
「原価率(げんかりつ)」とは、販売価格に対する原価の割合を表す指標です。たとえば、1,000円で販売する商品に対し、仕入れなどの原価が300円であれば、原価率は30%になります。
原価率(%)= 原価 ÷ 売価 × 100
この原価率は、ただの計算式ではありません。価格設定や利益確保の判断材料になる、とても重要な経営指標です。
開業前に原価率を理解しておくことで、「売れているのに赤字」という事態を防ぎ、無理のない価格設定ができるようになります。さらに、融資計画やビジネスプランを立てる際の説得力ある根拠にもなり、対外的な信頼性向上にもつながります。原価率の理解は、飲食業や小売業における経営の“共通言語”とも言える存在であり、従業員や仕入先との意思疎通にも役立つ要素です。原価率を日々意識することで、仕入れ交渉や値上げ判断の根拠にもなります。
「この価格で売っても大丈夫か?」と悩んだとき、原価率の知識があれば根拠を持った判断ができます。感覚的な値付けではなく、「利益を出すためにいくらで売ればよいか」を数字で把握できるため、仕入れやメニュー構成の改善にもつながります。
また、原価率を知っていれば、値引きやキャンペーンの際にも、どこまでなら赤字にならないかを予測できます。経営の舵取りをする上で、自信を持って判断できる材料が増えることは、大きな安心感につながります。
さらに、従業員に価格や仕入れの基準を共有しやすくなることで、現場レベルでの判断力も向上し、経営判断のスピードアップにもつながるでしょう。原価率を把握することで、仕入れ価格の変動や為替リスクにも柔軟に対応できるようになります。特に昨今は原材料価格の変動が大きいため、原価率を日頃から確認する習慣がリスク回避にも役立ちます。
原価率は、「原価 ÷ 売価 × 100」で求めます。この計算によって、仕入れに対して販売価格が適正かどうかがわかるようになります。
たとえば、原価300円の商品を1,000円で販売すれば、原価率は30%。逆に、「原価率30%にしたい」と考えるなら、原価が350円の商品は1,166円以上で販売する必要があります。
このように、「利益が出る価格」を事前に計算するための“逆算”は、価格設定の基本となります。原価率が変われば必要な売価も変わるため、仕入れやメニュー変更のたびにこの計算を確認する習慣を持つと安心です。
加えて、計算をシートやアプリで管理することで、複数商品を扱う店舗でも効率的に原価管理ができるようになります。原価率を定期的に見直すことで、原材料価格の高騰や業界動向に合わせた柔軟な対応も可能になります。
開業前に特に大切なのが、「いくらで仕入れたら、いくらで売れば利益が出るか」をシミュレーションすることです。原価から価格を決めるのではなく、利益を見据えた価格から逆算して原価の上限を決める方が、健全な価格設定につながります。
たとえば、「1,200円で販売したいメニューがある」とすれば、原価率30%で利益を確保するなら、原価の上限は約360円。これを超える場合は、仕入れルートの見直しや、他の原価が低いメニューと組み合わせたセット販売なども検討できます。
さらに、競合が似た価格帯で提供している商品との比較も、逆算の判断基準になります。数字をもとにしたシミュレーションを繰り返すことで、価格設定の精度は確実に高まります。
加えて、想定される値引きやキャンペーン時の価格変動も考慮しておくと、価格の柔軟性にも対応できます。たとえば、あるカフェでは500円のドリンクを提供しながら原価率を25%に設定しているのに対し、別の店舗では450円の商品で原価率35%という事例もあります。こうした比較から、自店の価格・原価率のバランスを見直すきっかけになります。
近年、同じ食材でも仕入れ値が1.2〜1.5倍に上昇するケースもあるため、価格設定には常に最新の仕入れ状況を反映させましょう。
原価率だけを見て価格を決めるのではなく、「FLコスト(Food & Labour)」の視点も大切です。FLコストとは、食材費(Food)と人件費(Labour)を足したもののことで、これが売上の60%以内に収まると経営が安定すると言われています。
たとえば、手間がかかる料理ほど人件費が高くなるため、その分原価率は抑えめにする必要があります。逆に、回転率が高い簡易な商品なら、多少原価率が高くても問題ない場合もあります。
つまり、価格設定は「原価率」と「FLコスト」の両方をバランスよく考慮することで、より実践的で現実的な判断が可能になります。原価が良くても人件費で赤字、という状況を防ぐためにも、早い段階から意識しておくことが重要です。必要に応じて、POSデータや人件費管理ツールを活用することで、より正確なコスト管理が実現できます。
FLコストの分析を習慣化すれば、忙しい時期や閑散期に合わせた柔軟なシフト調整や商品構成の最適化も可能です。
業種や業態によって、業態によって利益構造が異なる場合があり、原価率の「適正値」は一定ではありません。たとえば、テイクアウト店舗であれば、座席や接客スタッフが不要なため、設備や人件費などの固定費を大幅に抑えることができます。その分、原価率が30〜40%程度とやや高くても、十分に利益を出せるケースがあります。
一方、イートイン業態くまに熊日公園(例:カフェやレストラン)では、内装、光熱費、ホールスタッフなどにコストがかかります。そのため、原価率は25〜30%程度に抑えるのが一般的です。これにより、その他の運営コストとバランスをとりながら、継続的に利益を出せる体制を構築できます。
このように、原価率は単なる「数字」ではなく、店舗運営全体のコスト構造とリンクして考えるべき指標です。自分の店舗形態に合わせた目安を知ることが、無理のない経営への第一歩となります。
さらに、同業他社の成功事例や統計データなどを参考にすると、より現実的な判断ができるようになります。メニュー単位での原価率のばらつきも見直し、全体のバランスを最適化する工夫も必要です。
「うちの価格は安すぎ?高すぎ?」と気になる方も多いと思いますが、単純に他店と価格だけを比べるのは危険です。なぜなら、立地・コンセプト・原価率・サービス内容などの“コスト構造”が異なるためです。
たとえば同じパスタでも、駅前チェーンと郊外の個人店では、材料費や人件費、家賃がまったく異なります。したがって、価格もそれに応じて設定されるべきなのです。
重要なのは、「自分の店舗で必要な利益が出る価格設定かどうか」。他店の価格は参考にしつつも、自店の経費や目標利益をもとに、自分にとって適正な原価率を設定することが大切です。加えて、競合調査をする際は価格だけでなく、提供される価値やサービス内容にも目を向けることが、正しい比較につながります。
可能であれば、他店のメニュー構成や原材料にも目を向け、原価の背景まで観察する視点を持ちましょう。
価格設定に迷ったら、まず「原価率」を理解することがスタートラインです。業種や業態に応じた目安を参考にしつつ、利益を確保できる価格を逆算することで、安定した経営の土台を築くことができます。
特に開業前は、感覚や他店との比較だけで価格を決めず、「原価率からの逆算」をベースに価格戦略を立ててみてください。
数字が苦手でも、シンプルな計算から始めることで、経営の視界がぐっとクリアになります。
さらに、日々の売上やコストを「数字」で把握していくためには、POSレジや会計ソフトの活用もおすすめです。
なかでもCASHIERのPOSレジとfreee会計の連携により、売上・経費・利益がリアルタイムで可視化され、日々の判断がより的確に。価格戦略と合わせて、“数字に強い経営”を実現する一歩になります。
詳しくはこちらからご覧ください:
