
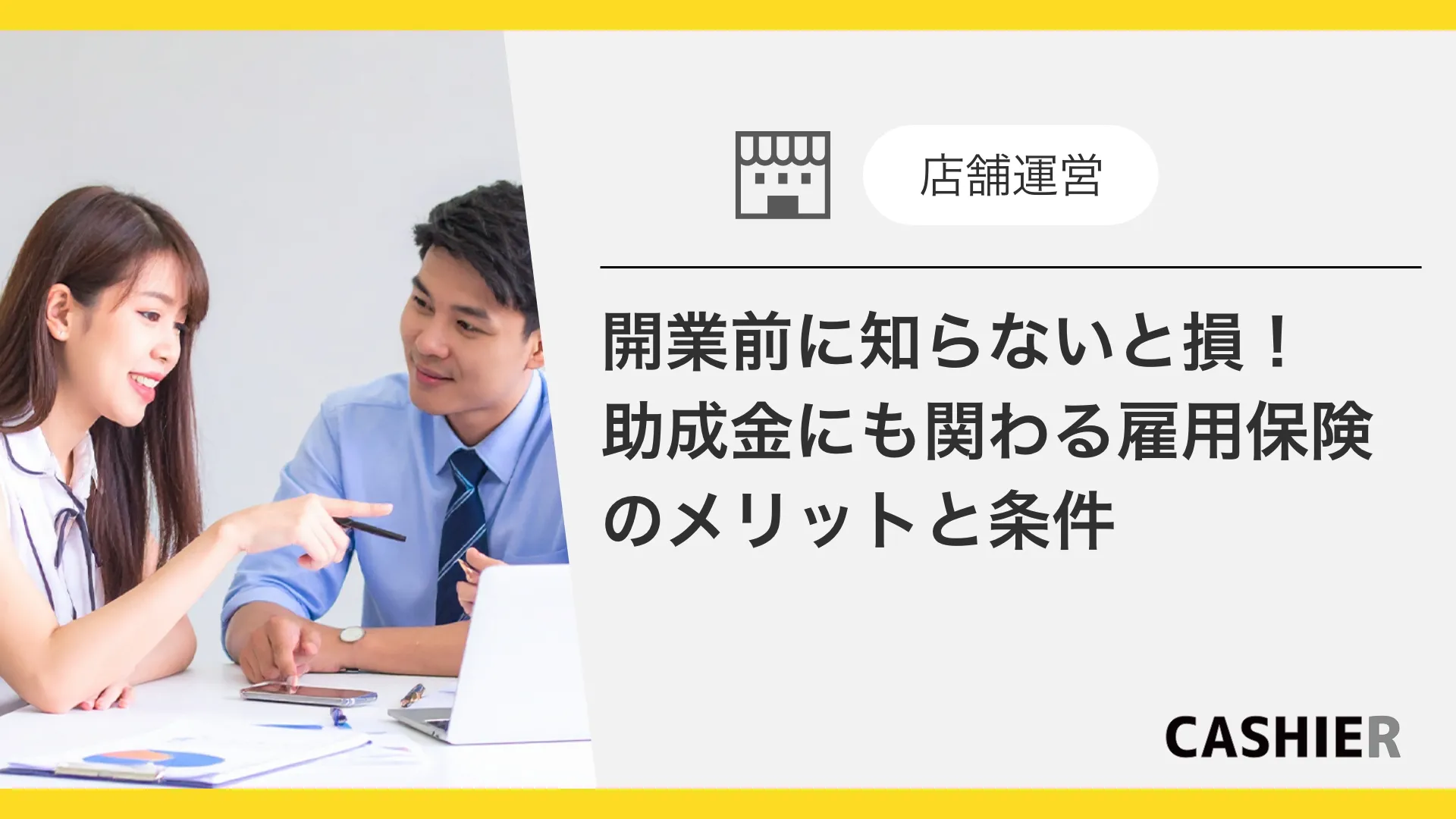 店舗運営
店舗運営 「うちは小規模だし、バイトしか雇わないから雇用保険は関係ない」そう思っていませんか?
実は、週20時間以上働くアルバイトやパートでも、条件によっては雇用保険への加入が義務になります。しかも、加入しておくことで助成金の申請や離職率の低下といった、経営者側のメリットも少なくありません。
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
本記事では、「そもそも雇用保険って何のためにあるの?」「誰が対象になる?」「手続きはどこでどうやるの?」といった疑問に対し、開業準備中のあなたが押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。 制度の仕組みや実務対応を理解しておくことで、あとから焦らずに済むだけでなく、経営のリスクヘッジにもつながるはずです。
開業を控えたタイミングで「雇用保険」という言葉を耳にする機会が増えるかもしれません。
雇用保険とは、労働者が失業した場合の生活・就職支援を目的とした公的な保険制度です。失業手当(いわゆる失業保険)のほか、育児休業給付や介護休業給付、再就職支援なども含まれています。
従業員にとって雇用保険に入っているかどうかは、働く上での安心感に繋がります。「もし働けなくなったらどうしよう」という不安が軽減され、定着率やモチベーションにもいい影響を与えます。
一見すると「従業員のための制度」に思えますが、実は経営者(事業主)側にも次のようなメリットがあります。
雇用保険は「労働者保護」のためだけでなく、加入することで、経営の信用力強化やリスクヘッジにもつながる制度です。
「社会保険と何が違うの?」という質問もよく聞かれます。
社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険などを指し、主に病気や老後に備える制度です。一方、雇用保険は「失業」や「育児・介護などで働けない期間」に備える制度です。
実は雇用保険も社会保険の一部です。しかし、目的や給付内容などの役割が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
「正社員じゃないから雇用保険は関係ない」と思われがちなバイト・パート雇用ですが、実は一定の条件を満たすと加入義務が発生します。
開業直後の店舗では「週2〜3日」「ランチタイムだけ」といった短時間勤務が多く、加入判断に迷うケースが少なくありません。
しかし、加入条件を満たしているにも関わらず未加入の場合、後から労働基準監督署やハローワークから指導を受けたり、助成金が受けられなかったりするリスクもあります。
事前に条件を把握して、トラブルを回避しましょう。
雇用保険の加入が必要になる条件は、主に以下の2点を満たす場合です:
この2つを満たしていれば、パートタイムの方やアルバイトでも、原則として加入が必要です。
たとえば「週4日×5時間」のような場合にも対象になります。
なお、「試しに短期間だけ雇ってみる」「様子を見ながら契約延長する」といった柔軟な雇用形態の場合でも、31日以上継続しそうであれば加入対象と判断されます。
一方で、
以下のようなケースでは雇用保険の加入対象外となる場合があります:
これらに該当する場合は、加入義務は発生しません。
ただし、「形式上は短期契約にしているが、実態は長期雇用」などという、形式上だけ免れるような契約は指導対象になる可能性もあるため、注意しましょう。
「加入義務だから仕方なく…」という気持ちで手続きを進めようとしている方もいるかもしれません。
ですが、制度を正しく理解して活用することで、経営面でも得をすることができます。
雇用保険の加入は、以下のような公的支援制度の前提条件になることが多くあります。
これらの制度を正しく活用することで、スタッフを雇うコストを実質的に軽減できる可能性があります。
雇用保険に加入していることは、採用活動においても信頼に繋がります。
特にバイトやパートは「万が一のときにどうなるか」を気にする層も多く、福利厚生のひとつとして雇用保険が与える安心感は大きいものです。
また、失業手当や育児休業給付などの制度があることで、働き続けやすい環境になり、早期離職を防ぐことにもつながります。
「制度の内容は分かったけど、実際どうやって手続きするの?」
これは、開業を目前に控えた方がよく感じる不安のひとつです。
焦らないためにも、実際に手続きをする時に備えて、必要な準備と流れを把握しておきましょう。雇用保険は義務であると同時にあなたの味方にもなり得る制度です。
雇用保険の手続きは、最初の雇用が発生した段階で以下の2つをハローワークに提出するところから始まります。:
この2つを従業員の入社日(雇用開始日)から10日以内にハローワークへ提出するのが基本ルールです。
開業届とは別に、「雇用が発生した時点」で手続きが必要になる点に注意が必要です。
また、法人の場合は登記完了後に、個人事業主であれば開業届提出後から手続き可能です。
項目 | 内容 |
いつ? | 従業員の雇用開始から10日以内 |
どこで? | 管轄のハローワーク(労働者の就業場所に基づく) |
何を? | 「設置届」+「取得届」+添付書類 (雇用契約書、マイナンバーなど) |
現在では電子申請にも対応しているため、開業準備中からe-Govなどで情報収集をしておくとスムーズです。
従業員の雇用保険について調べているうちに、「自分自身は加入できないの?」と疑問に思う方も少なくありません。特に開業直後は収入が不安定になりやすく、「いざというときの保障がないのは不安…」という声も聞かれます。
結論から言うと、原則として経営者本人は雇用保険の対象外です。
しかし、一部条件を満たす場合に限り、例外的に加入が認められるケースもあります。
雇用保険の対象となるのは、雇われている労働者です。そのため、個人事業主や法人の代表者(役員)は、一般的には加入できません。
ただ、法人役員でも以下のような実態が認められれば、労働者として扱われる可能性があります。
このような条件を満たしたうえで、ハローワークの認定が下りれば、役員であっても雇用保険の被保険者として認められる場合があります。ただしこれはあくまで例外であり、判断はケースバイケースです。
自分が対象になり得るかどうかは、開業準備の段階で最寄りのハローワークに相談しておくと安心です。
雇用保険は「加入義務を満たすためのもの」だけではなく、経営を支える制度でもあります。
開業前の今こそ、制度の基本と手続きを理解し、必要な準備を進めておきましょう。
特に以下の2点をチェックするだけでも、トラブルや機会損失を防げます:
さらに、雇用保険の対象判定や助成金申請では、スタッフの労働時間や雇用状況を正確に記録・管理しておくことが重要です。
たとえば、POSレジの「CASHIER(キャッシャー)」は、売上データをもとに適切な人材配置や商品管理を行うことで、業務負荷や人件費の傾向も把握しやすくなります。
CASHIERによる売上データの整備が、人事労務・会計全体の基盤づくりを後押ししてくれるはずです。
制度を知っているかどうかに加えて、それを“仕組み”として整えておくかどうかが、あなたの経営の安定と自由度を左右します。ぜひ活用してみてください。
詳しくはこちらから:
