
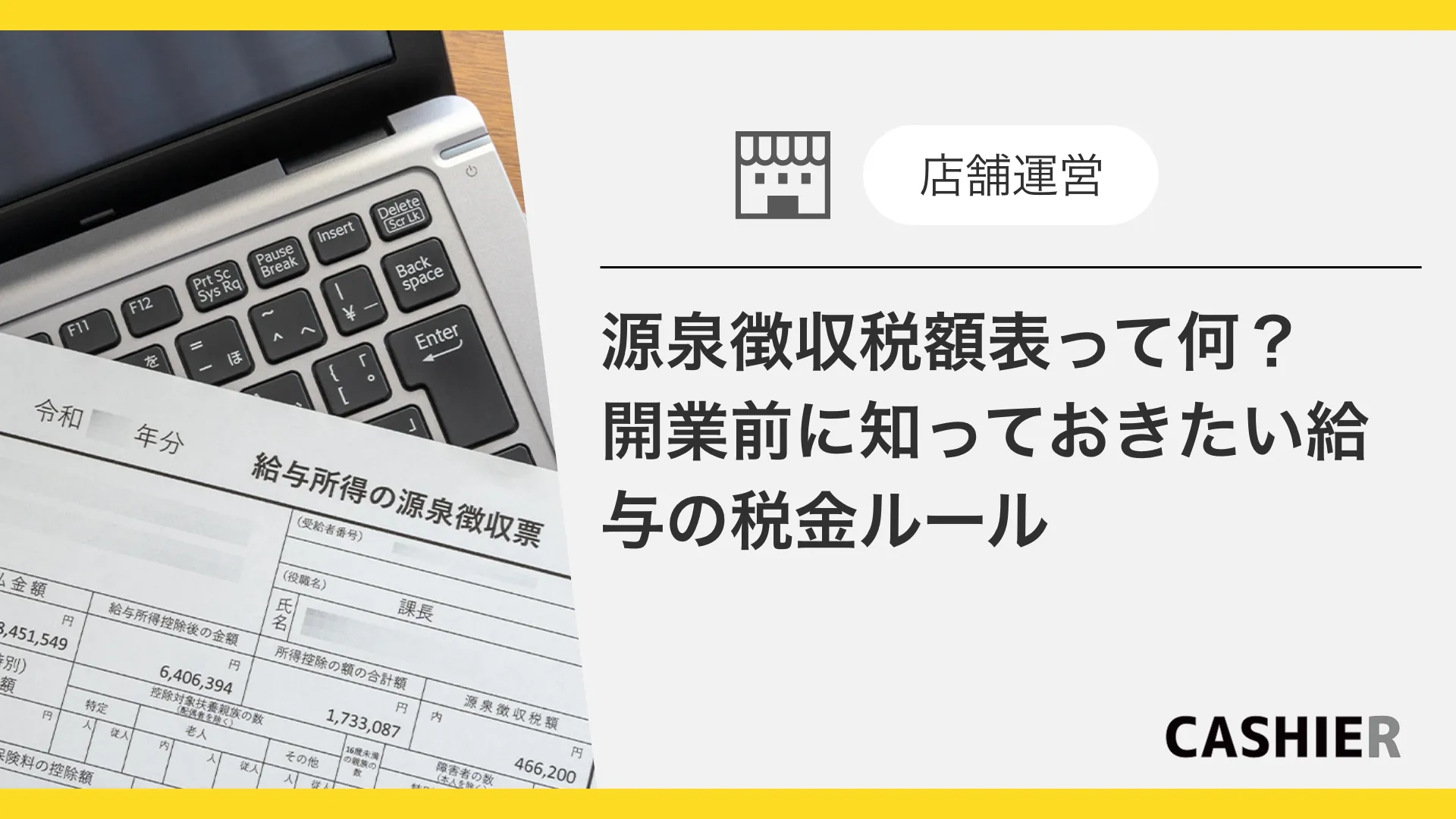 店舗運営
店舗運営 「アルバイトを雇う予定だけど、給与からどれくらい税金を引くの?」
そう悩んで検索しても、出てくるのは“源泉徴収税額表”という見慣れない表と、難しそうな専門用語の数々。しかも、「個人事業主でも源泉徴収しなきゃいけないの?」と不安になる方も少なくありません。
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
本記事では、開業・起業を目指す方に向けて、源泉徴収の基本から、税額表の見方や給与・賞与それぞれの計算方法、さらに自分に合った対応方法までわかりやすく整理します。
開業準備が進む中、「そろそろアルバイトを雇いたい」と考える方も多いのではないでしょうか。 しかし、いざ給与の支払いを想定したとき、「税金ってどうやって処理するの?」という疑問にぶつかります。 調べてみると出てくるのは「源泉徴収」や「源泉徴収税額表」という言葉。 なんとなく聞いたことはあるものの、どう使えばいいのかまでは分からず、不安になる方も少なくありません。
実際、源泉徴収は事業の立ち上げ期において見落とされがちなポイントのひとつです。 経営計画や物件探し、集客に目が向きがちな中で、「給与支払い時の税務処理」という地味な作業は、後回しにされがち。 しかし、従業員を雇う際の源泉徴収処理を誤ると、税務署から指摘が入る可能性もあるため、開業前に基本を押さえておくことがとても重要です。
「源泉徴収」とは、給与や報酬などの支払いの際に、支払う人が所得税などをあらかじめ差し引いて、受け取る本人の代わりに税務署へ納付する制度のことです。 たとえば、あなたが従業員に10万円の給与を支払う場合、そのうち数千円〜1万円程度を「所得税等」としてあらかじめ差し引いて支払い、翌月にその金額を国に納めます。 この仕組みにより、従業員側は確定申告の手間が減り、税務署としても安定的に税金を集められるようになっています。
「源泉徴収って、会社がやることでしょ?」と思われがちですが、実は個人事業主でも該当するケースがあります。 以下のような支払いをする場合、あなたが源泉徴収義務者となります:
つまり、法人かどうかにかかわらず、支払いの内容と相手によっては、あなたが税金を預かる側になるということです。
判断基準はシンプルです。 次のような場合、あなたは原則として源泉徴収義務者となります:
また、最初は1人しか雇っていない場合でも、税務署に開業届を出していることや、源泉所得税の納付義務があると案内されている場合は、該当する可能性が高いです。 不安な場合は、税務署や開業支援センターに相談すればすぐに確認することができます。
源泉徴収税額表は、従業員に給与や賞与を支払う際、どれだけの所得税を差し引くべきかを判断するための早見表です。 金額や扶養人数、申告書の提出有無などをもとに、あらかじめ定められた税額を一覧で確認できるようになっており、毎月の給与処理に欠かせない存在です。 例えば、月給が18万円で扶養親族が1人の場合、その条件に合った欄を見れば、源泉所得税の金額が一目でわかる仕組みです。 税務署から紙で郵送されるほか、国税庁のWebサイトでも最新版を確認することができます。
源泉徴収税額表には、支払いの種類に応じていくつかのパターンがあります。大きく分けて以下の3種類があります。
※フリーランスに源泉徴収を行う場合、月額表/ 日額表/ 賞与に関する税額表は使いません。代わりに、「報酬・料金・契約金等の支払調書」に基づく、所定の「定率計算(10.21%)で徴収します。 同じ従業員であっても、月給は月額表、賞与は賞与表、単発の手当は日額表といったように、支払い形態に応じて適切な表を選ぶ必要があります。
税額表を見ると「甲欄・乙欄・丙欄」という用語が出てきます。それぞれの意味と使い分けは以下の通りです。
・甲欄:扶養控除等申告書を提出している人に適用。
→ 主に本業で働いている従業員や、雇用契約に基づく正社員・アルバイトが対象です。
・乙欄:扶養控除等申告書を提出していない人に適用。
→ 副業者や短期アルバイト、掛け持ちバイトの従業員などが対象。甲欄より税率が高めです。
・丙欄(日額表):日払いや臨時的な勤務のある従業員に適用。
→ 支払いが1日単位で行われる場合に使用され、金額も日額ベースで設定されています。
初めて見ると混乱しがちですが、「誰がどの申告書を出しているか」「どんな雇用形態か」を確認することで、自ずと適用する欄が決まってきます。
給与支給時に源泉徴収税額を計算する場合、まず確認すべきは支給形態が月給制か日給制かという点です。
例えば、月給制で扶養が1名の従業員に対して18万円支払う場合は、月額表(甲欄)の該当行を見れば、その月に差し引くべき所得税額が明示されています。 税額表は、月給や日給が変動した場合にも柔軟に対応できるよう作られており、一定のルールに従えば、特別な計算式を使わずとも判断が可能です。
賞与(ボーナス)の支給時には、通常の月給とは異なり、賞与専用の源泉徴収税額表を使用します。 この表は、「直前3ヶ月の平均給与額」と「扶養人数」を基に税率を割り出し、賞与に対して課税する金額を算出する仕組みです。 具体的なステップは以下のとおりです:
この方式は「累計課税」と呼ばれ、毎月の給与と一時的な賞与を区別して課税することで、年間を通じた税負担の平準化を図るものです。 注意点として、給与と賞与を同時に支給する場合は別々に計算が必要なため、税額表の選び方と処理の順番には十分気をつけましょう。
従業員を雇ったら、まず最初に行うべきは「扶養控除等申告書」を記入してもらうことです。これは、本人とその家族構成(扶養親族)などを申告してもらう書類で、税額の決定に直接関わります。 この申告書が提出されているかどうかで、税額表の「甲欄」を使うか「乙欄」を使うかが決まります。提出されていれば「甲欄」、されていなければ「乙欄」と覚えておけばOKです。 申告書は、毎年1月または雇用開始時に提出してもらう必要があります。国税庁のWebサイトからPDFをダウンロード可能で、紙での保管も義務付けられています。
次に確認するのが給与の支払い形態です。大まかに分けて、「月給制」と「日給・日払い制」があります。
支払い方法に合わせた税額表を選ぶことで、正確な源泉徴収額が簡単に判断できます。「丙欄」は一見すると特殊に思えますが、短期アルバイトなど日雇いのケースでは標準的な扱いです。
最後は、実際の給与・日給・賞与の金額と、申告書・扶養人数の情報をもとに税額表の該当箇所を探して確認します。 例として、以下のように進めます:
この一連の流れを覚えておけば、税額の判断に大きく悩まずにすむようになります。
「やっぱり自分ひとりじゃ不安…」という方にとって、税理士への相談は非常に安心できる選択肢です。 特に以下のような状況では、プロの手を借りるメリットが大きくなります:
税理士に依頼すれば、源泉徴収だけでなく、年末調整や確定申告、経理全般まで一貫してサポートしてもらえるため、長期的な視点で安心感があります。
「専門家に頼むほどではないけど、自分で全部計算するのは大変…」 そんな方には、クラウド型の給与計算ソフトの活用がおすすめです。 特に中小規模の事業者に人気なのが、
これらのツールでは、従業員情報と給与金額を入力すれば、自動で源泉徴収額や社会保険料を計算し、帳票出力まで対応してくれます。税額表の該当欄を探す手間もなく、初心者でも安心して使えます。 また、法改正にも自動対応してくれるため、最新の税率にアップデートされているのも大きな安心材料です。
「全部は任せたくないけど、税金のことだし間違えたくない」 そんな方は、自分で初めて、途中からプロに頼む方法もおすすめです。 まずは自分で税額表の基本構造を理解し、簡単な処理からスタート。 不安な箇所や複雑な処理が出てきたときだけ、スポットで税理士に相談することで、費用を抑えながらも安心して運用できます。 実際、開業当初は自力で処理し、後に税理士に移行する事業者も多く、自分の事業ステージやリソースに合わせて柔軟に対応することが重要です。
源泉徴収税額表は、一見すると複雑でとっつきにくい印象を受けがちです。
「甲欄・乙欄・丙欄」や「給与・賞与別の表」など、初めて目にすると混乱するのも無理はありません。
しかし、実際には「雇った人が申告書を提出しているか?」「月給か日給か?」「どのくらいの給与額か?」という基本的な情報を整理するだけで、必要な欄は自然に絞り込めます。
まずは該当欄を確認するところから始めて見て下さい。
どうしても不安がある場合は、税理士や給与計算ソフトを頼ってもまったく問題ありません。今は自動計算や帳票出力ができる便利なクラウドツールも充実しており、事業者の負担は年々軽くなっています。
大切なのは、「分からないまま放置しない」こと。
開業前の今のうちに、最低限の構造やルールを押さえておけば、将来的なトラブルや不安を未然に防ぐことができます。
雇用を検討している方は、まずは「源泉徴収税額表」に一度目を通し、自分の事業に必要な対応を整理してみましょう。
▶ 令和7年分の源泉徴収税額表はこちら
国税庁の公式サイトでは、税額表や申告書のフォーマットも公開されていますので、あわせて確認しておくとスムーズです。
▶ 国税庁の公式サイトはこちら
さらに、開業の際に欠かせないのはPOSレジや会計システムです。
CASHIERでは、店舗の成長を助けるPOSレジシステムや、お会計周りの機器を取り扱っています。あなたのお店に最適なPOSシステムのご提案や、初期費用を抑えたい、売上データを活用したいなどのお悩み相談も無料でご対応させていただいております。
これから店舗を成長させたいとお考えの方は一度相談をしてみてはいかがでしょうか。
その他、電子チケットシステムや店舗運営、イベント運営などにも幅広く対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
CASHIERのさらに詳しい情報はこちら↓
リンク:https://cashier-pos.com/
