
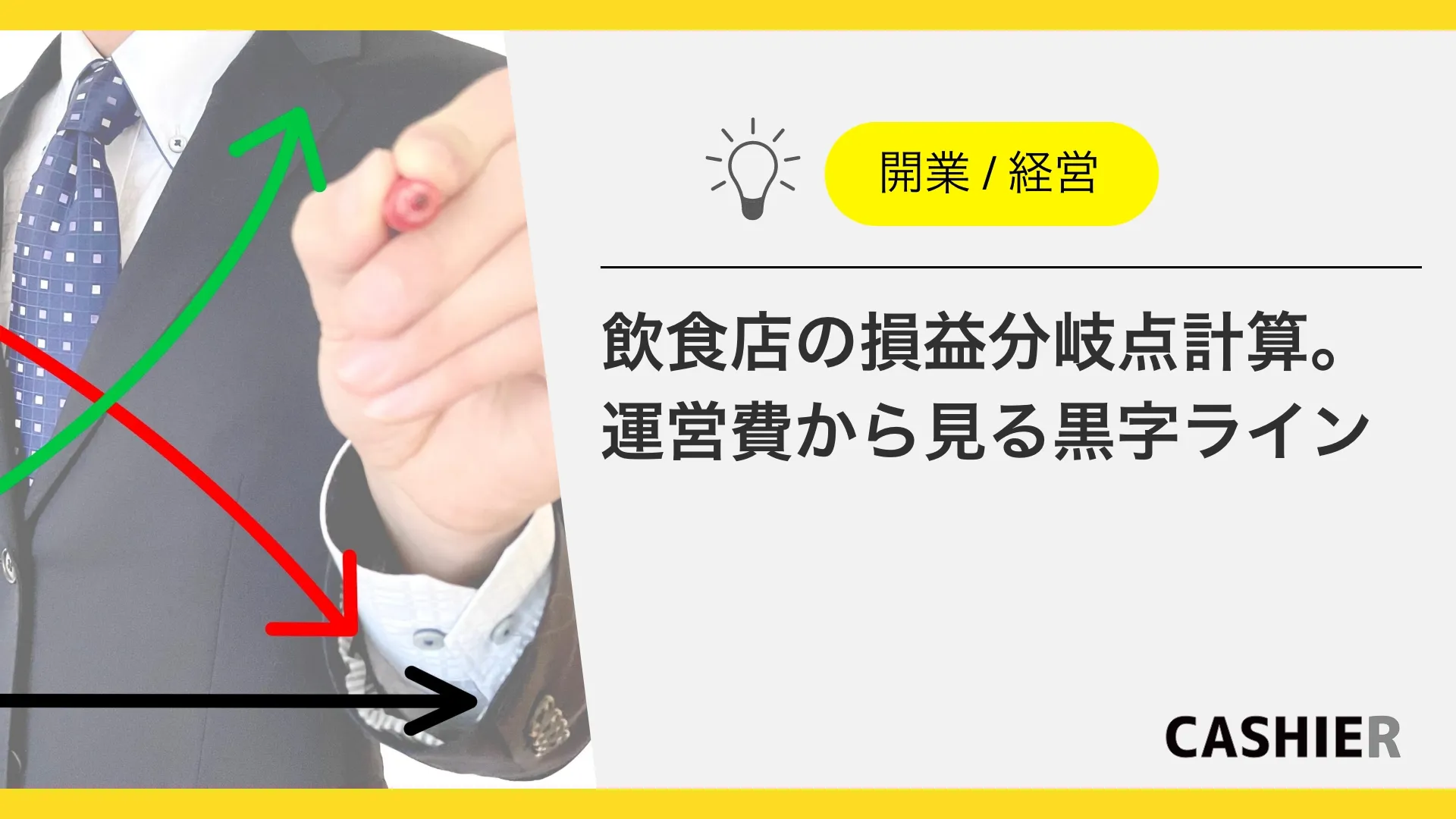 開業/店舗経営
開業/店舗経営 飲食店を開業・運営するうえで欠かせないのが、「自店はどれくらい売上を上げれば黒字になるのか」を把握することです。その答えとなるのが損益分岐点。固定費と変動費を正しく区分し、計算すれば、赤字と黒字のボーダーラインが明確になります。
数字に苦手意識がある方でもあなたの店の必要売上高が具体化し、開業計画や日々の判断にそのまま使える“道しるべ”が手に入ります。
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
本記事では、損益分岐点の基本、固定費・変動費の具体例、計算式、シミュレーションまでをステップで解説。さらに損益分岐点比率・安全余裕率を用いて経営の安定性を数値で把握する方法も紹介します。
損益分岐点は、店舗の売上=費用となり利益がゼロになる境界線です。ここを超えれば黒字、下回れば赤字となります。
実務ではまず費用を固定費と変動費に分け、変動費率(変動費 ÷ 売上)を算出します。そして、以下の式で損益分岐点売上高を求めます。
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷(1 − 変動費率)
この式の意味は、売上 ×(1 − 変動費率)=限界利益が固定費をちょうど回収できる点を導き出すものです。限界利益率を高める(原価・手数料の最適化、メニューMIX調整)ほど必要な売上は下がります。
光熱費や人件費の一部の扱いは迷いやすいので、売上ゼロでも払うか?という基準で判定し、基本的に支払う分は固定費に、増減した分は変動費に分類すると運用でブレにくくなります。
最初に区分ルールを固定化すると、その後の計算ブレが大幅に減ります。
固定費(売上に依存しない)
・家賃・共益費/通信・POS・保守サブスク/保険料/減価償却/店長・正社員の基礎給/光熱の基本料金
変動費(提供量・売上に比例)
・食材費/ドリンク原価/包材・消耗品/キャッシュレス・デリバリー手数料/繁忙帯の追加シフト/光熱の従量分
迷いがちな項目の扱い
・人件費:最低運営に必要な人員=固定、ピーク対応=変動
・光熱費:基本料金=固定、従量分=変動
・清掃・リネン:定額=固定、数量連動=変動
店舗内でこの定義を共有し、月次で振り返り調整していくことが重要です。
変動費率は「抜け・偏り」を潰すほど精度が上がります。
変動費率=(食材+包材+決済手数料+デリバリー手数料+変動的シフト+従量光熱等)÷売上。
正確に行うための3つのチェック項目:
このチェックをすることで、実際の営業に近い変動費率になり、損益分岐点のブレが小さくなります。
損益分岐点は「固定費を、売上から変動費を差し引いた残り(=限界利益)でちょうど回収できる水準」です。
この関係を数式で表すと、次のようになります。
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷(1 − 変動費率)
たとえば、固定費が100万円で、変動費率が43%の場合、
100万円 ÷(1 − 0.43)= 約175万円
つまり、月175万円の売上を超えると黒字になるということです。
さらに、平均客単価が1,100円なら、175万円 ÷ 1,100円 = 約1,600人/月
月に26日間営業する場合なら、1日約60人が目安になります。
ここまで出せば、必要客数(=損益分岐点売上÷平均客単価)や時間帯別の入店目標にブレイクダウンできます。計算値は“正解”ではなく“設計の基準”。仕入れや人件費が変われば数値も動くため、毎月見直して更新することが大切です。
理論だけでなく、実際に数字を当てはめると損益分岐点の重要性が一気に理解できます。ここでは、固定費・変動費率・客単価を設定して、必要売上や必要客数をステップごとに逆算してみましょう。
このシミュレーションを通じて「黒字ラインまであとどれくらい売上が必要なのか」「1日あたり何人の来客が必要なのか」が具体的に見えるようになります。
また、算出後は「安全余裕率」を見ることで、売上が落ちても赤字に転落しない余裕の範囲を把握できます。これらの数値は、開業計画や融資説明、日々の営業改善の指針として使える実践的な指標なので確認しておきましょう。
たとえば、固定費が100万円、変動費率が43%(=食材30%+変動人件10%+決済手数料3%)の場合。
このときの損益分岐点売上高は、
100万円 ÷ (1−0.43) = 約175.4万円。
つまり、月175万円の売上があればトントン(利益ゼロ)になります。
平均客単価を1,100円とすれば、
175.4万円 ÷ 1,100円 ≒ 1,595人/月。
26日営業(週1休)なら1日あたり約61人、営業時間6時間なら1時間あたり約10人。
この数字が「赤字と黒字の分岐点」です。
ここまで求めることで、席数・回転率・滞在時間・提供スピードなど、どこを改善すれば効率的に黒字を超えられるかが具体的に見えてきます。
損益分岐点を出したら、次に確認すべきなのが「損益分岐点比率」と「安全余裕率」です。
たとえば実際の売上が220万円の場合、
損益分岐点比率は約79.7%、安全余裕率は約20.3%となります。
これは「売上が2割落ちても赤字にならない」状態を意味します。
安全余裕率を指標にすることで、広告・人員・仕入れなどへの投資判断をより安定的かつ的確に行えます。
たとえば安全余裕率が5%しかなければ、固定費の増加や値上げは大きなリスクになります。しかし20%以上あれば、販促投資や新メニュー開発など攻めの施策に取り組む余地が生まれます。
つまり、安全余裕率とは「経営の余力」を示す数値です。この数字を根拠にすることで、無理のない投資判断と持続的な店舗運営につなげることができます。
損益分岐点を出したあとは、超えるためにどうするかを具体的に設計します。
売上は「客数 × 客単価 × 回転率」で構成されるため、どこに注力するかを決めましょう。
この3要素のいずれかを少しずつ改善するだけでも、損益分岐点を超える確率は大きく上がります。経営は「客単価+100円」「回転+0.2回」だけで、月売上は10万円単位で変わることも珍しくありません。
重要なのは、自分の店舗はどこを動かせば効果的かを数値で判断できる状態をつくることです。
損益分岐点売上高は固定費 ÷(1−変動費率)で決まります。よって、固定費を減らす/変動費率を下げる/売上を増やす の3つが基本方針になります。
実際に飲食店が行える改善アプローチを「固定費」「変動費」「売上設計」の3つの方法ごとに整理しましょう。
大切なのは方法を明確にし、店舗の実情に合わせて優先順位をつけることです。すべてを一度に変えようとするのではなく、費用対効果の大きい順に一歩ずつ進めてみてください。
固定費は毎月必ず発生するため、一度決めると柔軟に動かしづらい項目です。
とくに物件やリース契約は長期で固定化する傾向がありますので、開業前に検討しましょう。
「売上が上がらない」ときに真っ先に見直すのは変動費ですが、固定費の見直しこそ実は長期的な利益構造を変える力があります。
変動費は日々のオペレーションでコントロールできる領域です。
飲食業ではFLコスト(Food=食材費、Labor=人件費)が支出の大部分を占めるため、仕入れ・調理・提供の一連の流れを可視化し、ムダを抑えることが基本になります。
変動費の削減は削ることではなく、無駄を減らすこと。
品質やサービスを落とさず、売上1円あたりの利益率を上げる設計をしていき、同じ売上でも利益を残すことが目的です。
最後に、損益分岐点を下げるための売上強化です。
単に集客を増やすのではなく、既存客の単価・回転・再来店率を高めるほうがコスト効率は良く、利益率の改善に直結します。
この3方向の取り組みは短期・中期・長期で分けて進めると効果的です。
たとえば、短期は「回転率アップ」、中期は「単価アップ」、長期は「再来店率アップ」というように、店舗のリズムに合わせて重点を変えるのが現実的です。
このように、損益分岐点を下げるためには、固定費・変動費・売上の3要素を同時に見直す視点が欠かせません。
数字は経営の“結果”ではなく“道しるべ”。
毎月のデータをもとに、どの要素がどのくらい動いたかを確認しながら改善を続ければ、損益分岐点は確実に下げていくことができます。
最も多いのが、固定費と変動費の区分が毎月ズレてしまうケースです。たとえば光熱費や人件費は、季節や営業スタイルによって変化するため、一定ではありません。
こうした場合は以下のように整理します。
このように、売上ゼロでも払うか?を基準に分類するとズレを減らすことができます。
さらに、季節や時間帯ごとのデータを蓄積して加重平均をとることで、より実態に近い損益分岐点が導けます。
「原価率を下げれば利益が出る」と考えるのは危険です。
原価を下げることで、料理の満足度が落ちますし、客単価や回転率が下がれば、結果的に利益は減ります。
飲食店では原価率・人件費・回転率・席数のバランスを総合的に見て、利益構造を捉えることが重要です。
また、損益分岐点が下がっても、資金繰りが安定していなければ経営は続きません。
原材料の支払いサイト、家賃や給与の支払日など、キャッシュの流れを把握しておくことが不可欠です。
損益分岐点の活用は、「計算して終わり」ではなく、「毎月の経営確認の軸にする」ことがポイントです。
POSレジや会計ソフトのデータを連携して、固定費・変動費・変動費率・売上を確認し、毎月の損益分岐点を確認します。週次・日次レベルで把握しましょう。
この流れを習慣化すると、数字を「見る経営」から「動かす経営」へと変わります。
損益分岐点を定期的に見直すことで、施策や戦略を常にデータで裏付けられるようになります。
損益分岐点は、経営者だけが知っておくべき数字ではありません。
シフト設計や原価管理を担うスタッフと共有し、「今月はこのラインを超えよう」「材料ロスを1%下げよう」といった現場レベルの行動目標に落とし込むことで、店舗全体が同じ方向に動けるようになります。
こうした“数字の共有”を支えるのが、CASHIER POSのような売上データ管理ツールです。
CASHIERでは、日・週・月単位での売上や時間帯別・商品別データを自動で可視化できるため、固定費や変動費の分析、損益分岐点の把握が格段にスムーズになります。
さらに、商品登録やメニューごとの売上推移を確認することで、「どの商品が利益を押し上げているのか」「どの時間帯に人員を集中すべきか」といった損益分岐点を下げるための具体策まで見えてきます。
数字を“現場の共通言語”にし、POSデータから日々の行動へ落とし込むこと。
それが、損益分岐点を超えるための最も確実で、継続可能な経営改善の第一歩です。
