
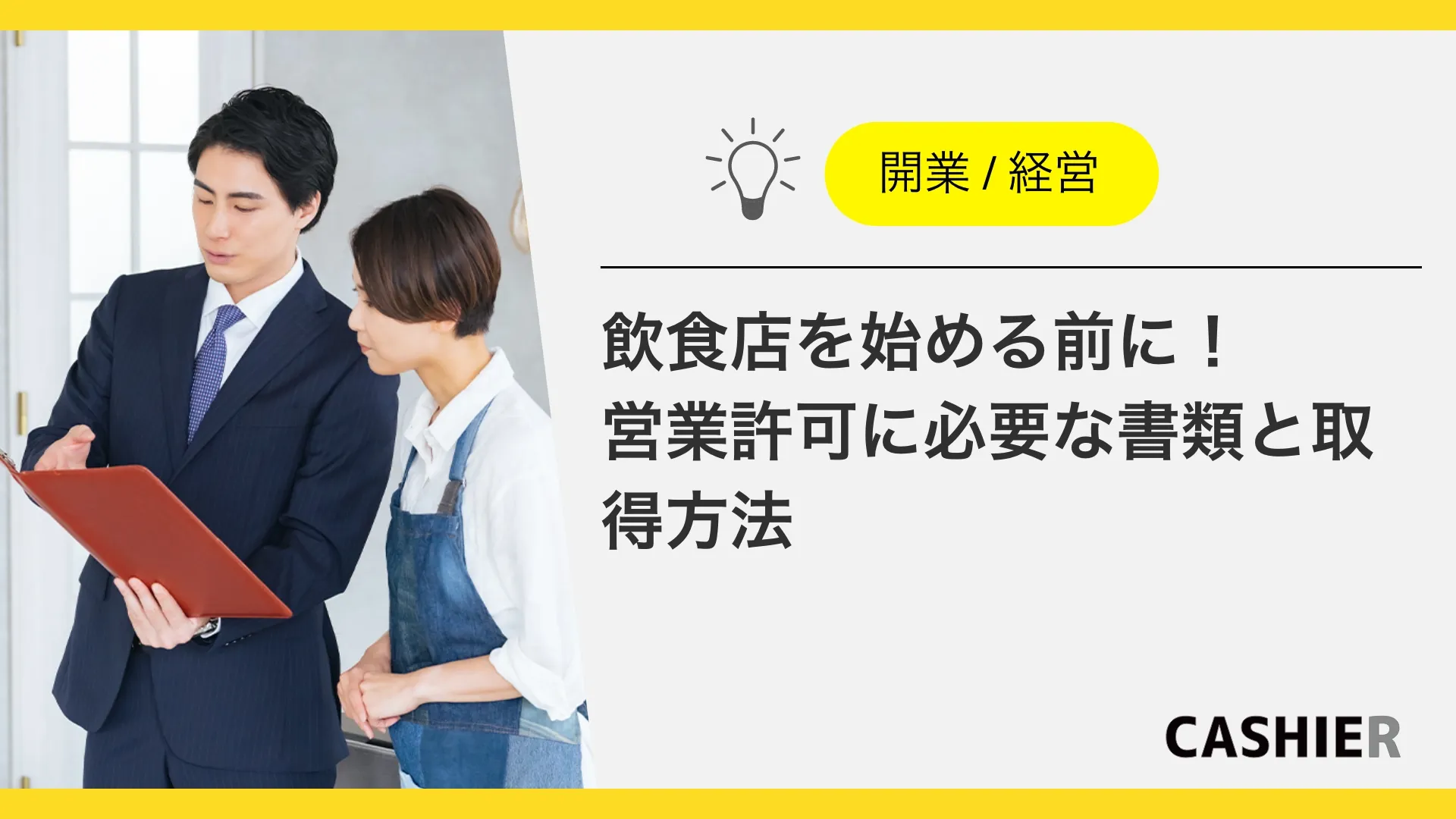 開業/店舗経営
開業/店舗経営 飲食店を開業するには、まず「営業許可」を取得しなければ営業を始めることはできません。
しかし実際に準備を進めてみると、「どんな書類が必要なのか」「手続きの順番は?」「いつまでにやればいい?」と疑問が重なり、不安を抱える方が少なくありません。
さらに、保健所・税務署・自治体など提出先が複数に分かれているため、初めて開業する人にとっては全体像がつかみにくく、「何から手をつけるべきか分からない」という状況になりやすいのが現実です。
手続きの遅れや工事のやり直しが発生すると、開業スケジュールに大きく影響するため、早めの情報整理と段取りがとても重要です。
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
この記事では、飲食店営業許可に必要な書類と取得までの流れを、5つのステップに分けてわかりやすく解説します。 さらに、多くの開業者がつまずきやすい「内装工事のやり直し」や「書類不備による遅延」など、よくある失敗例と対策についてもまとめています。初めての開業でも迷わないよう、必要な準備を整理した開業前の実用ガイドとして活用いただける内容です。
飲食店を開くうえでの最初の大きなステップが、保健所から交付される「飲食店営業許可」です。これは、厨房設備や水回り、衛生管理の体制などが食品衛生法に基づく基準を満たしているかを確認し、問題がなければ発行されるものです。厨房のシンク数や手洗い設備の位置、調理スペースの確保状況など、想像以上に細かい基準を満たす必要があり、事前知識がないと「どこから準備すればいいのか分からない」と戸惑う方も多い部分です。
実際、「自宅のキッチンに少し手を加えれば何とかなるだろう」と考えていたものの、いざ保健所に相談してみると基準を満たさず、別の物件を探すところからやり直しになってしまった、というケースもあります。特に、テナントビルや商業施設の一角を借りる場合、建物そのものの設備条件が営業許可に影響することもあるため、物件選びの段階から“営業許可が取れるかどうか”を意識しておくことが重要です。
特に、開業間近になって工事の不備が見つかり「許可が下りない」というケースは珍しくありません。オープン日が迫るタイミングでのやり直しは大きな痛手となるため、この許可取得の重要性を理解し、計画的に進めていくことがとても大切です。
飲食店では、お客様の口に入る料理を提供するため、衛生管理の徹底が欠かせません。調理器具の洗浄場所や食材の保管環境、調理導線の安全性など、日常では意識しにくい部分にも多くのリスクが潜んでいます。保健所は、これらの衛生基準が継続的に守られる環境が整っているかを確認し、許可を通じて「この店舗は安全な運営体制にあります」と保証します。
万が一、食中毒などの事故が起きた場合も、どのような設備環境でどのような管理体制がとられていたのかを検証する必要があります。営業許可を取得しておくことは、その意味でも「一定の基準を満たした環境で運営している」という一つの証拠になります。
営業許可は形式的な手続きではなく、お客様に安心して食事を楽しんでもらうための“信頼の証”です。開業後にトラブルを起こさないためにも、基準を理解したうえで設備を整えておくことは非常に重要です。
無許可で営業した場合、食品衛生法違反として行政処分の対象となり、営業停止命令や罰金が科される可能性があります。さらに、口コミサイトやSNSが発達した現在では、無許可営業が明るみに出ると一気に拡散され、店舗の信用回復は困難です。
テナント契約によっては、「法令違反が発覚した場合は契約解除」といった条項が設けられていることもあります。そうなると、単に罰則を受けるだけでなく、出店の場そのものを失ってしまうリスクもゼロではありません。
開業後のブランドや信頼を守るためにも、許可取得は必ずクリアしなければならない基本のステップ。開業者としての責任を果たす意味でも、事前の準備をしっかり行うことが求められます。
営業許可の申請には複数の書類が必要になりますが、内容を理解して整理すれば決して難しくありません。
まず中心となるのは保健所で提出する書類で、以下のような内容が求められます。
平面図は、厨房・客席・トイレ・手洗い場などの配置が分かる具体的なものが必要です。図面は不動産会社や内装業者から提供されるものをベースにしつつ、実際に設置する設備を反映させておくと保健所での確認もスムーズです。
また、設備の配置が保健所の基準を満たしていなければ、工事のやり直しにつながってしまうため、事前に図面を用意しておくことがとても重要です。最近は、各自治体のホームページから申請書の様式をダウンロードできるケースも多いため、まずは所轄の保健所のページを確認し、必要書類の一覧をプリントしてチェックリスト化しておくと安心です。
営業許可の申請とは別に、税務署での「開業届」や「青色申告承認申請書」の提出、法人の場合は都道府県税事務所での「法人設立届」も必要になります。提出先が複数に分かれているため、「営業許可は保健所、税務の手続きは税務署と自治体」と役割を整理し、開業準備と並行して進めることで後の手間を減らすことができます。
費用に関しては、自治体ごとに多少の違いがありますが、申請手数料は一般的に1万5千円前後。食品衛生責任者講習は1万円程度、水質検査が必要な場合は数千〜1万円ほどです。書類作成から許可交付までは通常2〜3週間程度を見込んでおくと安心ですが、混雑状況や自治体によって変わるため、具体的なスケジュールは事前に保健所へ確認しておきましょう。
営業許可を確実に取得するためには、「どの順番で手続きを進めるか」が非常に重要です。
飲食店の開業準備は、内装工事・設備導入・メニュー試作など多くの作業が同時並行で進むため、許可申請に関する手続きを後回しにしてしまう人も少なくありません。しかし、食品衛生責任者の資格取得や保健所への事前相談、必要書類の準備、現地検査の実施など、一つでも抜けてしまうと開業スケジュールが大きく狂う恐れがあります。
そこでここでは、営業許可までの流れを「大きな5つのステップ」として整理し、それぞれのフェーズで何をすべきかを順番に解説します。この順番を理解しておくことで、余計な手戻りや工事のやり直しを防ぎ、安心して開業準備を進められるようになります。
最初のステップは、「食品衛生責任者」の資格を取得することです。
これはすべての飲食店で必須の資格であり、1店舗につき1名以上の配置が求められます。自治体が実施する講習会に参加すれば、原則1日で取得できますが、人気の開催地では予約が埋まりやすく、直前になると希望日に受講できないケースもあります。
この資格証は営業許可申請の際に提出する必要があるため、物件が決まった段階でなるべく早く日程を確保しておくことが大切です。とくに開業日が決まっている場合は、資格取得が遅れるだけで許可申請にも影響が出るため、開業準備の中でも最優先で行うべき作業と言えます。
次に行うべきなのが、店舗の図面を持参して保健所へ「事前相談」に行くことです。
これは営業許可取得において最も重要と言っても過言ではありません。厨房のシンクの数、手洗い場の位置、食材の保管スペース、調理動線など、保健所が定める基準は細かく決められており、独自の判断で工事を進めてしまうと、後になって改善指示を受ける可能性があります。
事前相談では、図面を見ながら「この配置は問題ないか」「追加工事が必要か」といった点を担当者から直接アドバイスしてもらえます。これにより、工事完了後にやり直しが発生するリスクを大幅に減らすことができます。内装業者に任せきりにせず、開業者自身が基準を理解しながら進めることが大切です。
事前相談が終わったら、次は営業許可申請に必要な書類を揃えます。
申請書や店舗の平面図、食品衛生責任者の資格証の写し、賃貸物件であれば契約書のコピー、井戸水を利用する場合は水質検査成績書など、提出すべき書類は多岐にわたります。ひとつひとつは難しいものではありませんが、どれか一つでも不足していると申請そのものが受付されず、予定していたスケジュールが大きく遅れてしまう可能性があります。
特に、平面図は設備や動線が分かるように具体的に描かれている必要があり、雑な図面は再提出を求められることもあります。提出前に「必要書類リスト」を作成し、一つずつ確実に確認しておくことが、開業準備をスムーズに進めるためのポイントです。
申請書類の提出後に行われるのが、保健所による「現地検査」です。
担当者が店舗を訪れ、厨房の設備配置や衛生状態、調理スペースの清潔さ、手洗い場の位置などを細かく確認します。事前相談の段階で基準をクリアしていれば問題が生じることはほとんどありませんが、清掃や衛生管理が不十分な場合は改善を求められることがあります。
また、検査は希望通りの日程で予約できるとは限らず、繁忙期には数日〜1週間ほど待つこともあります。オープン日が決まっている場合は、検査と許可発行までの時間を逆算し、余裕を持ってスケジュールを組むことが大切です。
営業許可とは別に、税務署や自治体での手続きも開業前後に必要です。
個人事業主であれば「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署へ、法人の場合は都道府県税事務所で「法人設立届」も提出します。これらの手続きは営業許可申請と直接関係はありませんが、開業後の会計処理や税務管理に関わるため、許可準備と並行して進めておくと後々の負担が軽くなります。
営業許可の取得では、開業者が気づかないままつまずいてしまうポイントがいくつもあります。特に多いのが「内装工事の進め方」です。
たとえば、シンクの数が基準を満たしていなかったり、手洗い場の配置が不適切だったりすると、保健所から改善を求められます。工事が終わった後で「やり直し」ということになると、費用も時間も余計にかかり、開業スケジュールに大きく影響します。こうしたトラブルは、開業者が“工事の前に保健所へ相談していない”ことが主な原因です。工務店や設計会社も経験はありますが、最終的な判断を行うのは保健所です。オーナー自身が主体となって確認する姿勢が欠かせません。
書類の不備による申請遅延もよくあります。資格証のコピーを忘れたり、水質検査書類が不足していたり、図面に必要な情報が抜けていると、申請そのものがストップしてしまいます。こうした小さなミスを防ぐためには、早めに書類をそろえ、写しの作成や内容チェックを丁寧に行うことが大切です。「いつかやろう」と思っているうちに時間だけが過ぎてしまうので、具体的な日付を決めて書類準備に着手することをおすすめします。
また、開業日を決める際には、許可が下りるまでの日数と現地検査のタイミングも考慮しておく必要があります。「オープン日ありき」で逆算するのではなく、「許可が無理なく取れるスケジュールか」という視点も持っておくと、結果的に落ち着いて準備を進めることができます。スケジュールに余裕を持つことで、万が一の修正にも対応できます。
営業許可取得のポイントは、何よりも「段取りの良さ」と「事前準備」です。
資格取得、図面相談、書類準備、申請、現地検査という一連の流れを正しい順番で進めることで、開業準備は驚くほどスムーズになります。
書類は一つのファイルにまとめて整理し、抜け漏れを防ぐ体制を作っておくと安心です。紙のファイルに綴じる方法でも、クラウドストレージでフォルダを分ける方法でも構いませんが、「どこに何があるか自分がすぐに分かる状態」にしておくことが大切です。また、許可が下りるまで2〜3週間を見込み、店舗のオープン日から逆算してスケジュールを組むことで、焦りによるミスを未然に防げます。
開業準備は同時に複数の作業が進んでいくため、「何を優先すべきか」が分かりにくい部分もあります。しかし、今回紹介した流れに沿って一歩ずつ進めていけば、営業許可の取得は確実に前へ進んでいきます。もし不安なことがあれば、「こんなこと聞いてもいいのかな」と思わずに、早めに保健所へ相談してみてください。担当者と顔なじみになっておくことも、結果的には大きな安心材料になります。
飲食店の営業許可は、書類や手順こそ多いものの、事前に流れをつかんでおけば決して難しいものではありません。
特に、工事前に保健所へ相談することや、必要書類を早めに揃えておくことは、開業準備をスムーズに進めるうえで大きな助けになります。小さなミスが開業日の遅れにつながることもあるため、丁寧な段取りが成功の鍵です。
そして、許可が無事に下りた後には、レジ・売上管理・注文フローといった「日常の運営」を整える段階に入ります。初めての店舗運営では、会計まわりの混乱やスタッフの負担、オペレーションの属人化が起こりやすいものです。
そうした開業後の不安を軽減したい方には、POSレジ・セルフレジ・券売機まで一つのシステムで管理できる CASHIER が心強い味方になります。
まずは営業許可の準備を確実に進めつつ、開店後の運営まで視野に入れた環境づくりを進めてみてください。
その積み重ねが、お店の安心と継続につながっていきます。
