
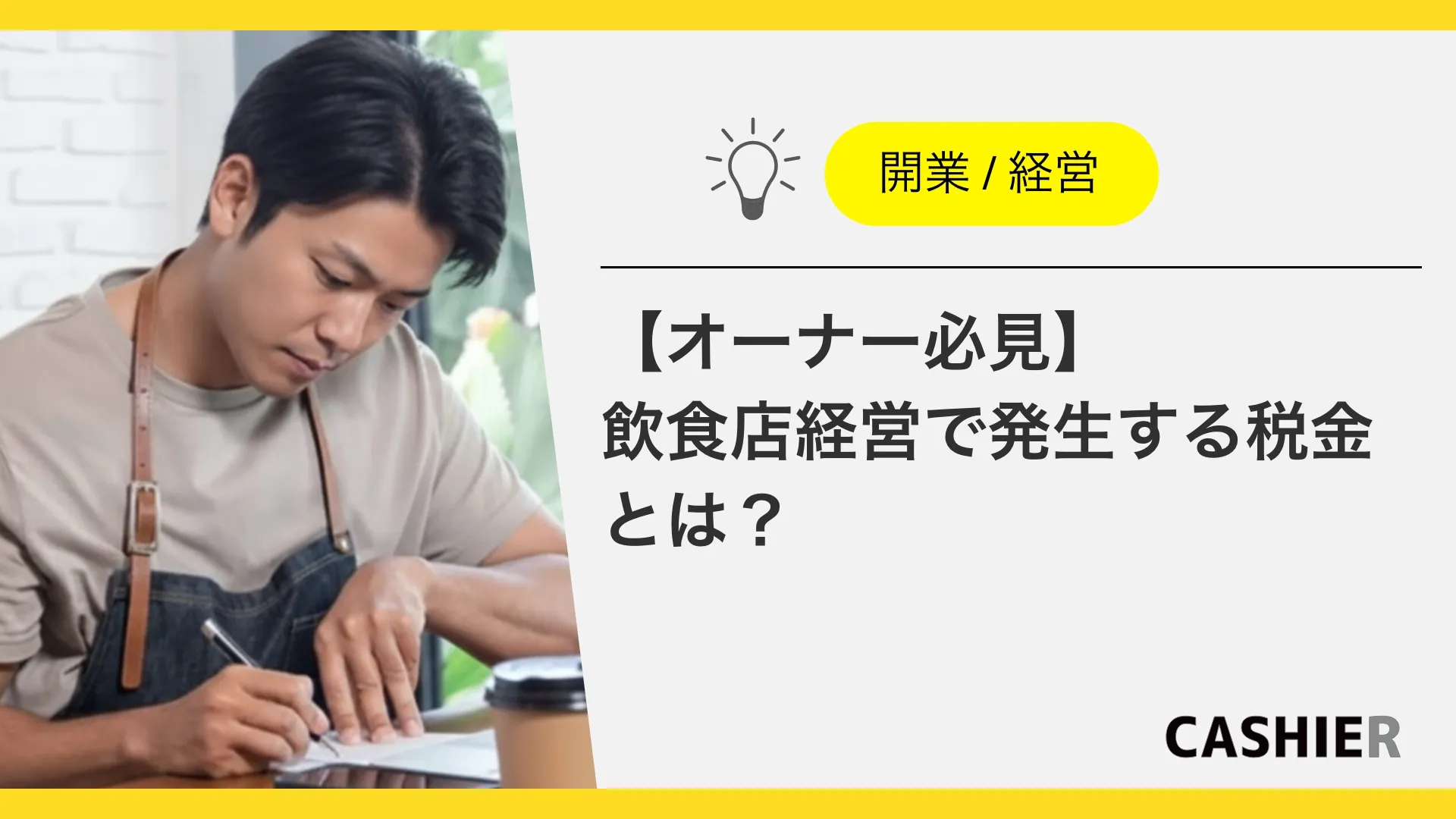 開業/店舗経営
開業/店舗経営 飲食店を開業したいと思ったとき、多くの人が最初につまずくのが「税金って、何がどれくらいかかるの?」という点です。
個人で始めるか法人を立ち上げるかによって税金の種類も変わり、さらに軽減税率・インボイス・消費税還付などの制度も絡んできます。
こうした仕組みを理解せずに開業を迎えると、思わぬ出費や還付の機会を逃すことも。
「開業してから慌てないために」今のうちに、税金の全体像を押さえておきましょう。
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
この記事では、開業前に知っておくべき飲食店の税金の基本を、 個人・法人・共通の3つの視点でわかりやすく整理します。 さらに、軽減税率の実務ポイントや、初期費用を抑えるための消費税還付の仕組みも解説。 数字や税金が苦手な方でも理解できるよう、実例を交えて丁寧に紹介します。
飲食店を開業する際、個人事業主として始めるのか、法人として設立するのかによって、
納める税金の種類や仕組みが大きく異なります。
一方で、どちらの形態でも共通して関係する税金もあり、開業前に全体像を把握しておくことが大切です。
ここでは、個人・法人・共通の3つの視点から、飲食店経営に関わる主な税金を整理します。
個人で飲食店を開業する場合、主に関係するのは所得税・住民税・個人事業税の3つです。
売上から経費を差し引いた金額(=所得)に応じて課税され、所得が高いほど税率が上がる「累進課税」が採用されています。
また、確定申告の方法によっても負担が変わり、青色申告を選択すれば最大65万円の控除を受けることが可能です。
このほか、自治体ごとに課される住民税、一定額以上の所得がある場合に発生する個人事業税なども押さえておきましょう。
「帳簿付けや申告が不安…」という場合は、クラウド会計ソフトを導入すれば自動で仕訳・集計が行え、開業初年度でもスムーズに対応できます。
法人として飲食店を設立する場合、中心となるのは法人税・法人住民税・法人事業税の3種類です。
個人のような累進課税ではなく、利益に対して一定の税率(法人税等の実効税率は規模・条件により変動。最新の公表値を確認しましょう)が課されます。
加えて、都道府県・市区町村に納める地方税も発生します。
法人の場合、役員報酬や経費計上の範囲が広く、節税や資金管理の自由度が高いのが特徴です。
一方で、設立登記や決算申告などの事務コストは増えるため、「安定した利益が見込めるタイミングで法人化」するケースが一般的です。
将来の規模拡大や多店舗展開を視野に入れるなら、早めに税理士や専門家へ相談しておくと安心です。
個人・法人の形態にかかわらず、共通して関係するのが消費税・印紙税・固定資産税です。
まず、消費税は年間売上が1,000万円を超えると納税義務が発生しますが、
開業初期の設備投資が多い場合には、課税事業者を選択して消費税還付を受けることも可能です。
次に、印紙税は契約書や領収書などを発行する際に必要で、金額に応じて200円~60,000円ほどの印紙を貼付します。
※電子契約など、契約形態によっては印紙税が不要となるケースもあります。
また、固定資産税は店舗や土地、設備を所有している場合に課されます。
不動産を借りて開業する場合でも、内装や厨房機器などを自社で所有する場合は対象になるため注意が必要です。
リースや割賦契約の場合は契約内容で課税関係が異なるため、事前に確認しておきましょう。
これらの税金は避けられないコストとして、事業計画や資金繰りにあらかじめ組み込んでおくことが重要です。
飲食店の経営では、消費税の扱い方がとても重要です。
特に「軽減税率」や「インボイス制度」は、日々の会計処理やお客様とのやり取りに直接関わる仕組みです。
正しく理解しておかないと、税率を間違えたり、取引先とのトラブルを招くこともあります。
ここでは、開業前に知っておきたい2つの制度の基本を整理します。
軽減税率制度とは、消費税率10%への引き上げに合わせて導入された仕組みで、
一部の品目や取引に対して8%の税率が据え置かれる制度です。
飲食店の場合、店内飲食は10%、テイクアウトや出前は8%という違いがあり、同じメニューでも提供方法によって税率が変わります。
たとえば、カフェでコーヒーを店内で飲むと10%ですが、持ち帰れば8%。
この区分を正確に処理するには、軽減税率対応POSレジの導入が不可欠です。
レジ上で販売区分を分けて登録しておくことで、会計時や申告時の混乱を防げます。
また、請求書や領収書にも税率を明記する必要があるため、会計ソフトと連携させておくとスムーズです。
軽減税率は一見小さな差に見えますが、誤ると後から修正が必要になることもあるため、開業前から設定を整えておきましょう。
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、
「消費税を正しく仕入控除できるようにする」ための仕組みです。
登録を行った事業者は「適格請求書発行事業者」となり、
取引先や仕入先に対してインボイス(適格請求書)を発行できます。
開業初期は売上が1,000万円未満の時、免税事業者としてスタートできますが、
仕入先や取引先がインボイス登録を求めてくるケースも多く、
登録しないと取引が制限されたり、発注先から敬遠されることもあります。
登録には税務署への届出が必要で、審査に数週間かかることもあるため、
開業準備の段階で登録すべきかどうかは判断しておくのが安心です。
判断に迷う場合は、取引予定の業者や会計担当者に早めに相談し、
BtoB比率・取引先方針・経理コストの3点から、自店の規模と将来像に合った選択をしましょう。
飲食店の開業準備では、内装工事・厨房機器・備品など、多額の支出が発生します。
こうした初期費用にかかる消費税の一部が「還付」として戻ってくる場合があるのをご存じでしょうか?
この制度を理解しておくと、資金繰りを少しでも楽にでき、開業初期の負担を軽減できます。
ここでは、消費税還付の基本と、開業前に押さえておくべきポイントを解説します。
売上で預かった消費税より、仕入や設備で支払った消費税が多い場合、差額が還付される仕組みです。
飲食店の開業初期には、設備投資や仕入れなどで大きな支出が発生するため、該当するケースも少なくありません。
ただし、還付を受けるには「課税事業者」である必要があります。
通常、売上が年間1,000万円以下の事業者は免税扱いですが、
自ら「課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで、課税事業者として登録できます。
この届出は開業届と同時に提出しておくのが理想で、タイミングを逃すと初年度の還付を受けられない場合もあります。
開業直後に高額な設備投資を予定している方は、必ずこの手続きを検討しましょう。
消費税の還付を受けるには、日々の取引記録や領収書の管理が欠かせません。
具体的には、仕入れや設備投資にかかった支出を会計ソフトで区分して記録し、
請求書・領収書などの証憑をきちんと保管しておくことが重要です。
また、インボイス制度の導入後は、仕入れ先が「適格請求書発行事業者」であることも要件になります。
つまり、インボイス未登録の事業者からの仕入れは控除対象外になる可能性があります。
これらの管理を手作業で行うのは負担が大きいため、
軽減税率・インボイス対応の会計ソフトやPOSレジを活用しておくと、記録漏れや計算ミスを防げます。
制度を正しく理解し、日常の記録を整えることが、スムーズな還付申請につながります。
飲食店の開業準備で意外と後回しにされがちなのが、税金や制度の対応です。
しかし、開業前に少しだけ意識して行動しておくことで、後々の負担を大きく減らせます。
ここでは、初心者でもすぐに実践できる税金対策の3ステップを紹介します。
開業準備の最初のステップは、開業届を提出するタイミングで税務署に相談することです。
「個人と法人、どちらで始めた方が良いか」「課税事業者になるべきか」など、
疑問点をこの段階で解消しておくと、後のトラブルを防げます。
特に、設備投資を予定している場合は「課税事業者選択届出書」を同時に提出できるか確認しておくと安心です。
税務署では無料で相談を受け付けており、担当者が制度や手続きを丁寧に説明してくれます。
開業届をただ出すだけでなく、今後の税務方針を相談する場として活用しましょう。
軽減税率やインボイス対応は、開業後の実務に直結します。
そのため、レジや会計ソフトを選ぶ段階で、軽減税率・インボイス対応済みのものを選ぶことが重要です。
たとえば、軽減税率対応POSレジであれば、店内飲食とテイクアウトを自動で区分でき、
税率ミスや集計漏れを防止できます。
また、会計ソフトと連携しておけば、仕訳や消費税申告も自動で処理され、
開業直後でもスムーズに確定申告が行えます。
税務を意識したツール選びは、「日常業務を楽にする」=「将来の税金対策」にもつながります。
インボイス制度は、取引先や仕入先との関係にも影響する重要な制度です。
開業前から登録するかどうかを判断しておくことで、後から取引条件で慌てるリスクを減らせます。
たとえば、取引先が「インボイス登録事業者とのみ取引する」としている場合、
登録しないと仕入控除が受けられず、取引を断られるケースもあります。
一方で、開業初期の売上規模によっては、免税事業者としてスタートする選択も可能です。
そのため、開業前に取引予定の業者へ確認し、
「いつ登録するのが最適か」を見極めることが大切です。
必要に応じて、会計ソフトや専門家に相談しながら進めましょう。
税金は「開業してから考えるもの」ではなく、開業準備の段階で整えるものです。
制度を理解し、ツールを活用することで「知らなかった」で損をするリスクを防ぎ、安心してスタートできます。
飲食店の開業を成功させるには、メニューや立地と同じように税金への理解が欠かせません。
個人・法人で異なる税金、共通して発生する消費税や印紙税、
さらに軽減税率・インボイス・消費税還付などの制度を、開業前から整理しておくことが重要です。
難しい専門知識をすべて覚える必要はありません。
軽減税率やインボイスに対応したPOSレジや会計システムを導入すれば、
販売・集計・申告まで自動化でき、ヒューマンエラーや申告漏れを防げます。
なかでもCASHIER(キャッシャー)は、
税率自動区分・インボイス対応・会計ソフト連携に対応し、
開業直後でも正確な売上データをもとに経営判断が可能です。
開業を控える今こそ、「税金対策」を経営準備の一部として考え、
制度とツールをうまく組み合わせて、安心してスタートを切れるお店づくりを進めましょう。
