
 店舗DX
店舗DX 自動釣銭機は、釣銭の計算や排出を自動で行ってくれるため、店舗の業務効率化に大きく貢献する便利な機器です。一方で、「釣銭の過不足」や「紙幣や硬貨の詰まり」などのトラブルが起きる可能性もあります。
トラブルへの対応が遅れると、レジ業務が停止し、顧客満足度の低下につながりかねません。
本記事では、自動釣銭機でよくあるトラブルやその対処法、使い方のコツを解説します。自動釣銭機の概要やメリット・デメリットなどを詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:【店舗必見】自動釣銭機のメリットとデメリット!導入で解決する悩みと注意点
▶︎店舗運営を止めない!セルフレジ・POSレジ・券売機のトラブル事例と速攻対策ガイド
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
この記事では、自動釣銭機のよくあるトラブルに関する情報を紹介しています。店舗の業務効率化に大きく貢献する一方で、過不足や現金の詰まりなどのトラブルが発生します。トラブルに対処するためには、事前の準備が大切です。レジを運用するうえで重要なポイントをまとめているので、ぜひ参考にしてください。

自動釣銭機には、以下のようなトラブルがよく見られます。
それぞれ見ていきましょう。
自動釣銭機の過不足は、「釣銭優先運用」を採用していることが原因です。スタッフが手動で預かり金を入力する必要があるため、入力ミスが起きやすく、過不足や違算につながります。
具体的な流れを見てみましょう。
入力ミスを防ぐには「入金優先運用」への切り替えが有効です。スタッフが現金の金額を入力する必要がなくなるため、ミスが発生しません。
トラブルの発見が難しい場合もあるため、釣銭の確認作業と再発防止策を徹底することが大切です。
自動釣銭機に大量の紙幣や硬貨を一度に投入したり、異物が混入したりすると、詰まりが発生することがあります。現金が詰まった場合、機器が正常に動作せず、レジが使えなくなります。
詰まりはスタッフが対応する必要がありますが、正しい手順を知らなければスムーズに解消できません。たとえば、CASHIERで取り扱っているグローリー社のN300の場合、以下の手順で詰まりの解消が可能です。
詰まりを解消する際は、無理に取り出さないよう注意が必要です。また、日常的に内部の清掃を行い、異物の混入を防ぐこともトラブル予防につながります。
自動釣銭機はPOSレジと連携して利用しますが、接続エラーが発生すると、決済処理が停止します。ネットワークやサーバーの障害が主な原因です。
接続エラーが発生した場合は、以下の方法を試してみましょう。
トラブルに慌てず対応できるよう、店舗スタッフ全員が基本的な復旧手順を把握しておくことが重要です。ただし、ネットワークやサーバーの障害は大規模なトラブルになる可能性もあるため、業者に対応を求めるのがよいでしょう。
セルフレジとして自動釣銭機を導入する場合は、お客様が精算後にお釣りを取り忘れるケースも少なくありません。取り忘れたお釣りを第三者が持ち去り、思わぬトラブルへ発展する可能性もあります。
お釣りの取り忘れを防ぐには、「釣り銭取り忘れアラート」機能を搭載した自動釣銭機の導入がおすすめです。ブザー音やランプによる通知によって、お客様自身が釣銭の取り忘れに気づきやすくなり、トラブルの防止につながります。
お釣りの取り忘れは思わぬトラブルの原因になるため、「釣り銭取り忘れアラート」機能にも注目して機器を選びましょう。
新紙幣が導入された場合、古い自動釣銭機では対応できず、利用できなくなることがあります。特に中古や旧式の自動釣銭機は、メーカーのアップデートが提供されない場合があるため注意が必要です。
新紙幣に対応するには、新紙幣対応の自動釣銭機を選定するか、定期的にアップデートを行う必要があります。また、読み取り機能のアップグレードを行うことで、偽造紙幣の検出精度も向上し、新紙幣への確実な対応が可能になります。
新紙幣対応には時間を要することも多いため、早めに対応準備を進めることが大切です。
自動釣銭機内の現金が不足すると、釣銭が出せなくなり、会計処理が中断してしまいます。現金不足になれば、スタッフが両替対応を行わなければなりません。
店舗内に現金の準備がない場合は、銀行まで出向かなければならず、さらに時間や手間がかかります。レジ前の混雑や会計待ちのストレスを招くだけでなく、顧客満足度の低下や売上機会の損失にもつながりかねません。
営業前やレジ締め時に釣銭の残量を確認し、不足が予想される場合は事前に十分な両替を済ませておくことが重要です。また、突発的な釣銭不足にも対応できるよう、店舗内に予備の釣銭を用意しておくと安心です。
セルフレジとして自動釣銭機を導入する場合は、機械の操作に不慣れなお客様が戸惑うケースは少なくありません。特に高齢者や機械操作に苦手意識のある方は、操作に時間がかかり、レジ待ちの列ができる原因になります。
お客様をサポートするために、スタッフをレジ近くに配置するのがおすすめです。スタッフが操作サポートをスムーズに行えるように、マニュアルの設置や事前に操作トレーニングを実施しておくことも大切です。
セルフレジの導入により、レジ担当者が不在となることで、万引きや支払い忘れといったリスクが高まります。特に混雑時には、チェックの目が届きにくくなるため、対策を怠ると売上損失につながります。
対策としては以下の方法がおすすめです。
このような対策を講じることで、トラブルの多くは防げるので、店舗の状況に合わせてできることから取り入れてみてください。
自動釣銭機に異物が混入するトラブルもよくみられます。ゴミや外国の紙幣・硬貨などの異物が機械に混入すると、詰まりや動作エラーを引き起こす原因となります。
トラブルを防ぐには、日常的な点検と清掃が欠かせません。また、異物が混入した際の取り出し方法についても、スタッフに共有しておくことが大切です。
たとえば、グローリー社のN300の場合は以下の手順で異物を取り出します。
異物を無理に取り除こうとせず、メーカー推奨の手順に従って処理することが機器の故障や事故防止につながります。
精査エラーとは、内部で紙幣・硬貨が詰まったり、計算ミスが発生したりする際に発生するエラーです。エラーが発生すると、「精査」ランプが点灯し、機器に表示される案内に従って再計算を行う必要があります。
異常が解消されない場合は、手動で現金を一度回収して再投入しなければなりません。たとえば、以下のような手順で行います。
精査作業中に違算が発生することもあり、操作ログを確認して原因を追跡することが求められます。異常が発生した際には、速やかに対応できるようスタッフにマニュアルを共有しておくことが重要です。
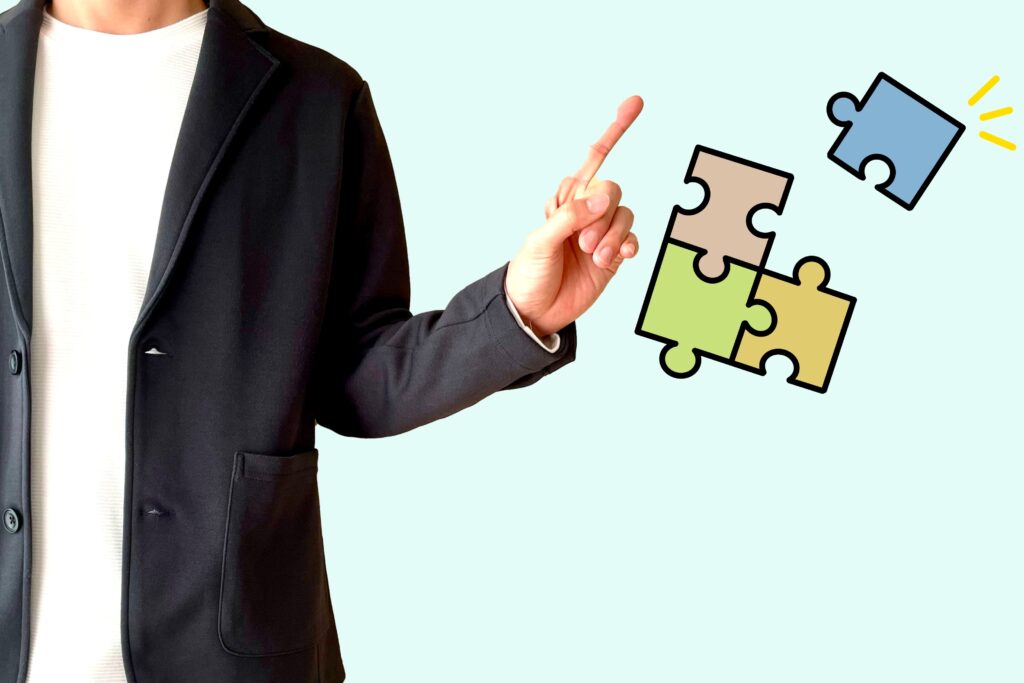
ここまで自動釣銭機でよくあるトラブルについて解説してきました。ここでは、そのトラブルを未然に防ぐための解決策を解説します。
自動釣銭機でトラブルが発生した際、迅速に対応できるよう、事前にオペレーション体制を整えることが重要です。トラブル対応に時間をかけてしまうと、その間、レジ業務が止まり、レジ待ち時間が増えてしまいます。
そのため、自動釣銭機のエラーや、操作方法がわからないお客様に対応できるように体制を整えておきましょう。
たとえば、
など、対応フローをあらかじめ決めておくことが大切です。自動釣銭機は精密機器なので、どうしてもトラブルは発生します。現場で混乱が起きないよう、事前にオペレーション体制を整備しておきましょう。
自動釣銭機のトラブルを防ぐためには、定期的な機器メンテナンスも大切です。自動釣銭機の不具合の多くは、内部の汚れや紙幣・硬貨の詰まりによって引き起こされます。
そのため、日常的な清掃や定期的な点検が欠かせません。メーカーが推奨する保守頻度や方法に従い、投入口や排出口の清掃を行いましょう。
また、内部のメンテナンスは専門的な知識が必要になる場合もあるため、定期的にメーカーへ点検依頼するのをおすすめします。
自動釣銭機を導入する場合、複数台の設置を検討しましょう。1台のみで自動釣銭機を運用すると、故障した際に店舗全体の会計処理が止まるリスクがあるからです。
とはいえ、小規模店舗などはコスト面の負担から、複数台の導入が難しいこともあります。予算的に複数台の導入が難しい場合は、レンタルやリース契約がおすすめです。
リースやレンタル契約を活用すれば、初期費用を抑えて導入台数を増やせます。自動釣銭機を複数台設置することで、トラブル発生時の業務停止を防ぎ、サービス品質の維持が期待できるでしょう。
レジ締めを行う際は、釣銭機の残量を確認することが大切です。紙幣・硬貨の残量をチェックしておくことで、営業中の釣銭不足によるトラブルも防げます。
また、このタイミングで機器に異常がないかも確認しておくと、営業中に突然故障するといったトラブルも避けられるでしょう。スタッフごとにレジ締めのやり方に差が出ないように、作業手順をしっかりマニュアル化して共有しておくことも大切です。
お客様がセルフで会計を行う場面では、ちょっとした操作ミスがトラブルにつながることもあります。誰でも迷わず使える、わかりやすい自動精算機を選ぶことが大切です。
たとえば、画面がシンプルで見やすい、音声で次の操作を案内してくれるといった工夫があると、年齢を問わずスムーズに使えます。結果的に、スタッフがサポートに入る機会も減り、現場の負担も軽くなるでしょう。
自動釣銭機には「残置処理(残置回収)」という機能が搭載されています。これは営業終了後に、売上金と翌日の釣銭準備金を自動で仕分ける機能です。
本来であれば、翌日に使う釣銭を手動で計算・準備する必要があり、手間がかかります。残置処理機能を使えば、釣銭を機器内に残したまま売上金のみを回収できるため、釣銭の準備が不要です。
日々のレジ締め業務がグッと楽になるため、閉店後の業務を効率化したい店舗にとっては、大きなメリットとなるでしょう。
自動釣銭機のトラブルにすぐに対処できる、サポート体制が手厚い提供会社を選ぶことが重要なポイントです。営業中に不具合が発生すると、会計業務が滞り、売上に影響が出る可能性があります。
そのため、導入前から運用後のサポート体制を確認しておきましょう。
サポート体制が整っている提供会社を選べば、トラブル時にも安心して対応でき、店舗の業務を止めずに運用できるようになります。

自動釣銭機をうまく使うコツは以下のとおりです。
自動釣銭機には「入金優先運用」と「釣銭優先運用」という2つの運用方法があります。
入金優先運用 | 釣銭優先運用 | |
概要 | お客様が支払った代金を自動釣銭機に入金し、釣銭を自動で計算・排出する方式 | 会計金額を先に入力し、お客様に釣銭を支払って会計した後に預かり金を投入する形式 |
メリット | 金額入力ミスが起きにくい | 処理が速く、レジ待ちを減らせる |
デメリット | 釣銭優先運用と比較して会計スピードが遅くなる | 店員の入力ミスにより違算が起きやすい |
店舗のニーズに合わせて、正確性を重視するなら「入金優先」、スピード重視なら「釣銭優先」を選びましょう。
自動釣銭機は、会計部分を自動化できるため、セミセルフレジやフルセルフレジとして利用できます。それぞれの特徴とメリット・デメリットは以下のとおりです。
セミセルフレジ | フルセルフレジ | |
特徴 | 商品スキャンをスタッフが行い、会計をお客様自身が行う方式 | 商品スキャンから会計まで全てお客様が行う方式 |
メリット | ・キャッシュレス決済に対応できる ・会計時間が短縮する ・衛生面を強化できる ・スキャンミスが減る ・比較的高齢者でも利用しやすい | ・人件費を削減できる ・待ち時間を短縮できる ・スタッフは他の業務に集中できる ・回転率が向上する ・衛生面を強化できる |
デメリット | ・支払い忘れのリスクがある ・商品をスキャンする人材が必要になる | ・導入コストが高い ・お客様が操作に戸惑うケースがある |
導入店舗例 | 薬局・アパレル・小売・飲食チェーン店など | コンビニ・スーパー・無人店舗など |
セミセルフレジやフルセルフレジは、店舗の業務効率を大きく向上させるだけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。どのセルフレジを選ぶかは、店舗のニーズや規模、顧客層などを踏まえて判断することが大切です。
自動釣銭機は会計業務を効率化するうえで欠かせない機器ですが、トラブルが発生するケースもあります。
これらは自動釣銭機の運用中によく見られるトラブルです。しかし、運用方法の見直し(釣銭優先運用と入金優先運用)や定期的なメンテナンス、サポート体制を整えるなど、事前に対策を講じておけば、多くのトラブルは防げます。
CASHIERの自動釣銭機なら、もしものトラブル時にも万全のサポート体制が用意されています。自動釣銭機の導入を検討されている方は、ぜひ一度公式ホームページよりお問合せください。
